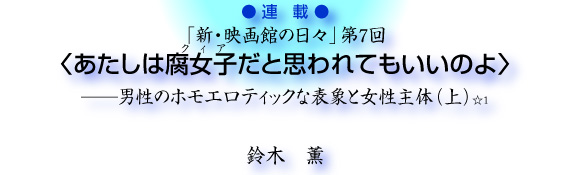本で埋まった丹尾さんの研究室を訪ねると「美術史ってたいてい、きれい事でしょ?」。辛辣だ。(…)戦争、漫画など学界が遠巻きにしてきたテーマに挑んできた。「戦争画にせよ、あったものをなかったことにせず、きちんと認識するのが第一の作業」との姿勢を取る。
著者の発言をこのインタヴュアーは、「きれい事」ではない「男色」研究もまた、「あったものをなかったことにせず、きちんと認識」しなければならない、義務としての行為であるかのようにまとめている。それを怠っては「昔」の「芸術」が味わえず、「理解が行き届かない」というわけだ。男色という主題は、「戦争画」と並べられることで、厄介だがなかったことにはできないものというニュアンスを帯びる。
院政期の男色と言えば、そのあたりの研究者の座談会か何かで、自分は同性愛者ではないが、といちいち断わっているのを昔読んだ記憶があるのだが、大橋洋一が報告している(前出「ゲイ文学」註参照)、「ある同性愛文学のシンポジウム」で「筆者以外の講師は全員、求められもしないのに、自分が同性愛者ではないこと、結婚していることを発言や発表の中で挿入的にコメントした」というのはそれと同じシンポジウムのことなのだろうか。気になりながら、雑誌が手元にないので確かめていないのだけれど。研究対象に魅惑されていません、趣味ではありません、「きれい事」ではないと承知しています、でも学者ですから、学問ですから、史実ですから、必要ですから、芸術ですから、文化ですから……というわけか。
「史実」であれば芸術・文化に影響「しなかったはずはない」、「無視すべきではない」とどこまでも腰が引けているこうした言説に対して、同性愛は「あったもの」ではなく「あるもの」であり、現に生きている人間が「美」や「芸術」に結びつけられなくてはならないいわれはない、と同性愛者が抗議するとしたら、それは当然のことである。だが、同性愛をはっきりと「あるべきではない」と決めつけるわけではない、この寛容な抑圧(記者本人も気づいていない)からは、この国でゲイ・リベレーションがゲイ文学に結びつかない理由の一端をも窺えるように思う。
それでは、高原英理が挙げていたような男性作家たちの、異性愛のオルタナティヴを示す(その一方でミソジニーの色濃い)「表象された同性愛」の世界はどこへ行ってしまったのだろう。ここではいかにも無責任に、消えたと思われた恐竜が鳥になっていたように、それは「やおい」として、つまり、あらかじめ女性が排除された領域への女性からの批評として、部分的には生き延びたのであると言っておこう。唐沢俊一は『男色の景色』に対する短い書評(2月1日付朝日新聞)で、「日本文化の通奏低音として隠されてきたこの美意識を思うとき、それがBL小説などにいかに影響を与え、かつ変容してしまったかも思い合わせられる気がする」と 、独特の鋭さでそのあたりの事情に(僅かながら)触れていた。
ゲイ男性自身によるゲイ文学がなりをひそめてしまった――というより、そんなものは日本近代文学に一度も存在したためしがないのだが(高原が挙げたような作家たちにしても、現実の同性への欲望を公言していた者はほとんどおらず、作品の内容が個人的性癖に帰せられることを避けると同時に、わかる者にはわかるという「反俗」の矜恃に支えられていた)――ともあれ、「そのような文学者」の作り出した月光に照らされた沃野だの果樹園だのは消え去って久しく、今や「女性がつくり楽しむ男性同士の性愛物語」(石田美紀『密やかな教育』の本文及び帯)という美意識のカケラも感じられない言葉で形容される荒地ばかりだ、と慨嘆する人間がいてもおかしくないが、それよりむしろ、そうした沃野があったことさえ知らない者が、当事者でない女がなぜゲイ表象をもてあそぶのかと言い出すのばかり目立つ昨今であるのは周知の通りだ。
「美童文化」のフィールドで、女は最初からアウトサイダーである。男色といい女色といい、それは男が「まなざしをむけ」るものだ。少年はいつか〈大人〉になることができるが、女は違う(だから「女子供」という)。女が性的主体の位置につくとは、太陽が西から昇るようなことなのだ。それは、今までは太陽が東から出る世界の話ばかりだったから、そっちについてはこれから存分に論じればよい、というようなものではない。もしそれが本当に記述されることがあれば、その時にはこの世界は今あるものとは別な何かに変わっていよう。
自分をリベラルだと信ずる者が、「私は異性愛者であるが同性愛者を差別しない」と思うのはたやすい。だが、「同性愛者を差別しない」とは、本来、「異性愛者である」という土台が掘り崩されるような体験ではないのか。しかし、「同性愛者」の方も、通常、「異性愛者」にそこまで要求はしない。というのも、「異性愛者」が混じりあわないアイデンティティに安堵の息をもらすのと同様、同性愛者も、「異性愛者」は異性を愛し、「同性愛者」は同性を愛するという自堕落な同語反復におさまりかえっているからだ。(上で「同性愛者」と呼んだのは、基本的に男性のことである。上の図式の中でレズビアンを考えると――実際、さかんに考えられているのだが――それはゲイ男性の女版にしかなりえない。)
この秩序の中で、女でありながら男性のホモエロティックな関係を想像し、性的快楽を得る「やおい」はどこに居場所を求めうるだろう。男性向けポルノにはレズビアンものというジャンルがあって、異性愛の一部として理解されている。では、これはその女版なのだろうか?
だが、同性愛者の場合同様、ここでも女は男の女版ではない。享楽する女の表象に女が同一化するのなら、まだわかりやすかったろう。あるいは、男のように能動的に快楽を追求するのであれば(女には淫らな女というポジションもある)。それらは男のヘテロセクシュアリティを、都合よく補完するものであるからだ。だが、「腐女子」はそのどちらでもない(いささか話を急ぎ過ぎたかもしれない。今、筆者は、「腐女子」という実体があたかもあるかのように書いてしまった……)。
『男色の風景』巻頭の口絵には、愛らしい少女めいた弘法大師の絵姿が使われている。筆者はたまたま、同書のもとになった論考が連載中だった「新潮」を開き、黒白の小さな図版として挿入されていたこれに目をひかれた。というのは、ある友人から、幼時に空海の生涯をたどるマンガ仕立ての説話「おだいしさま」を読み、生みの母以外ろくに女が登場せず、男同士で弟子を奪いあうような物語に強い印象を受けたこと、表紙を飾る、男でありながら女のように艶めかしい稚児大師こそ、人生の最初期に見出した〈美〉であったことを聞いていたからだ。こうした図像を「稚児大師」と称するのを、「余計な意味がまとわりつき、無用な連想を呼び起す」として、童形大師と呼ぶことを勧める「アカデミックな美術史」の言説を引き、「稚児は僧侶の愛欲の対象であった」と丹尾はきっぱりと言う。「稚児大師と呼ぼうと童形大師と名付けようと、かような図像は、当時の僧たちの目に、われらが現在見るよりも、ずっとなまめかしく映じたに相違なかった。」
なるほど、幼い目に、それは「われらが現在見るよりも、ずっとなまめかしく映じた」ことだろう。友人がもし男であれば、それは自らの(ホモ)セクシュアリティの起源としての物語を形成したかもしれない。異性愛体制に組み込まれる以前にかいま見たイコンの記憶。しかし彼女は女であるので、真魚さま(空海の幼名)で「やおい的なもの」に目覚めたと言うのだった。男色にherstoryはない。だがそれは公式にはないというにすぎない。
女性の観客が、(基本的には)ホモソーシャルでヘテロセクシュアルな規範に沿った「オリジナル」の創作物から、ふたりの男性の登場人物の組み合わせを抜き出して(カップリング/pairing)、プラトニックなものからハードな性行為をともなうものまで、両者のあいだのさまざまな形態のホモエロティックな関係を想像し、それを小説やマンガ、イラストレーションなどの二次創作に加工してセクシュアルな享楽を得る、という消費文化にはすでに30年以上の長い歴史がありますが、かつて(表層的には)マイナーな位置にとどまっていたこうした文化は、おそらくはインターネットの普及をきっかけに、現在はかなりグローバルなレベルで、映画の消費文化のひとつのメインストリームを形成しつつあるのではないでしょうか。
このように述べる鷲谷花は、映画『ヴァン・ヘルシング』について、「身体的なエロティシズムを担うのが、ほぼ男性の役割に限定されている」こと、「抑制もしくは排除される要素、それはリアルでエロティックな女性の身体で」あることを指摘し、「現在のメジャー映画における俳優の身体のエロティシズムの変容には、女性観客の能動的な欲望と、女性が主体となって作り上げてきた消費文化のありかたが深く関わっている」という仮設を立てる。近年のハリウッド製冒険活劇の特徴として、彼女は「受動的で無垢な美青年と、攻撃的で成熟した年上の二枚目の、あからさまには性的ではないものの、それとなく官能的な組み合わせ」を挙げ、「このような人物関係のパターンの好みの普及にあたって、やはり映画の消費文化としてのやおい/slash文化のメインストリーム化がひとつの大きな要因になっていることは想像に難くありません」と言う。その最大のきっかけは『ロード・オブ・ザ・リング』三部作で、「そんな少年たち、男たちは、友情から家族愛から屈折した兄弟愛から師弟愛から主従の愛からライヴァル関係まで、露骨に性的な肉体関係を除くありとあらゆるエモーショナルな絆で結びつけられているうえに、傷の手当て、肉体的・精神的苦痛へのいたわり、戦いの最中の助け合い、死にゆく友への親愛のしぐさなど、濃厚なスキンシップの描写が全編に詰め込まれ、観客に対して「萌えポイント」をたえず提供しつづけていました」。 さらに、「ひとつ重要なのは」と鷲谷は指摘する。「『オリジナル』の『LotR』自体に、やおい/slash文化における二次利用をあらかじめ前提としているかのような要素が多分に含まれていたことです。」
興味深い考察であるが、これが「女性向け」に特化されたものと見なしうるかどうかは微妙なところだ(ついでに言えば、映画の原作である『指輪物語』や、トールキンのもう一つの大作『シルマリリオン』が、すでにやおい的要素を多分に含むものであり、また、それが転倒した認識であることはすでに触れた)。「男同士の友情物語」とは、これまでにも数限りなく表象されてきたもので、彼女が指摘するような要素は、過去の映画にもふんだんに見出されるからである。そうした物語とやおいの境は、ホモソーシャルとホモセクシュアルの境が限りなく曖昧なように見きわめ難く、実のところ両者は《同じ品柄》でできている(直裁(的に性的な描写があるかどうかは、ある意味、実は関係がない)。むしろ、それが「やおい/slash文化における二次利用をあらかじめ前提としているかのような」と見えるようになったことが、それ以前にあったものを隠蔽しているのだ。そして次のことはぜひとも強調されねばならないが、そうした物語とは、もともと、男が作り、男の感情に訴える、男のためのもの――男性読者/男性観客向け――であった(とはいえ、「やおい文化」が顕在化する以前にも、女はひそかにそれを〈流用〉☆2してきた)。
デイヴィッド・M・ハルプリンは「英雄とその友人」(『同性愛の百年間』所収)という論文で、アキレウスとパトロクロス、ギルガメシュとエンキドゥ、ダビテとヨナタンという、成立年代と場所を異にする古典的男性カップルについて次のように述べている。
三つの物語伝統のすべては、二人の、二人だけの人物のあいだの親密な友情を特色としている。この二人の人物はつねに男性である。彼らは対を形づくるが、比較的二人だけで孤立している。[…]さらにこの関係は、[…]つねにその焦点が外側に向けられていて、栄誉ある行いの完遂とか、政治的目的の達成とかいった、その関係を超えて活動している目的を備えている。[…]英雄的友情はたんに二者関係であるだけではなく、位階的でもある。それは(アメリカのラジオやテレビの昔の聴視者には、ローン・レンジャーとトントの例からしておなじみの)仲間で、従僕で、親友のいる英雄の型を示しているのである。
私たちにとってもこれはおなじみの「人物関係のパターン」であり、鷲谷の言う差異ある男二人もまた、このヴァリアントに他ならない。これもまた女性の発明などでは――流用であっても――ありえないのである。
鷲谷の論考への「はてなブックマーク」コメントには、ゲイ男性であるブロガーの次のような指摘があった。
エロス対象としての男優の身体表象を構築するホモソーシャリティ/ミソジニー。なぜ男のエロスはホモソーシャリティの中でばかり表象されるのか(ゲイは不在なのか)という疑問が次に来るけれど……
名が無いと、薔薇はそう呼ばれたときのようによい匂いがしないだろうか。思い出してみよう、あまたのバディ映画の中で、「エモーショナルな絆」に結ばれ、「栄誉ある行いの完遂」のために「身を挺して」(☆3)いた男たちを。明白な敵同士として、あるいは味方であっても対立しながら、何らかの使命に携わるうち、関わりを深め、認めあい、惹かれあう男たち――しばしば「奇妙な友情」と呼ばれもするそうした関係を描いた映画やドラマなら、誰でも一つや二つ(あるいはもっと)思い当たるだろう。かつてゲイ男性はそこから読みうるものに炯眼を誇っていた(実は女たちにもそれは見えていたのだが)。あまりにも狭く定義されたゲイ・アイデンティティのためにそこに「ゲイの不在」しか見ないとしたら、そして、ありもしない同性愛を腐女子が捏造していると見なされてしまうとしたら、何という皮肉だろう。
「男のエロス」が「ホモソーシャリティの中でばかり表象される」のには、このホモフォビックな社会の、少なくとも主流文化では、友人関係だのとってつけたような女の恋人だので、異性愛に偽装されるという事情がまずあろう。だが、それにもまして、「ホモソーシャルな欲望」(セジウィック)は、「友情、家族愛、屈折した兄弟愛、師弟愛、主従の愛、ライヴァル関係」における「エモーショナルな絆」を通して描かれるとき、もっともよく表象されてきたのだ(☆4)。それを何と呼ぶにせよ、それは〈ゲイ/男性〉にオリジナルかつ独占的に属しはしない。そしてそれが友情と呼ばれる限り、ノンケの男たちもホモセクシュアル・パニックに陥ることなく「萌えポイント」を心地よく愛撫されることができる。むろん彼らは、そこに確かに現前しているものを、あくまで見まいとするだろう。かつてフロイトは、片手で拒み片手で受け入れようとするヒステリーの女の身ぶりを記述したが、ストレート男性も名づけは拒否しながら享楽だけはしっかり受け取ってきたのだ。
有形無形の検閲下では友情と呼ばれていたものは、しかし、もろい境界をひとたび越えれば、明示的にセクシュアルな関係へたやすく変容を遂げる。ニュージーランド映画『神々の黄昏』は傷ついた英国兵とマオリの戦士の、まさしく「傷の手当て」という「スキンシップ」にはじまり、介抱が愛撫に、格闘が抱擁に似るおなじみの過程を経て、二人きりの森の奥で「露骨に性的な肉体関係」に至る話であった。互いに一語も通じない敵同士の、水の流れと小鳥のさえずりに囲まれた、束の間の心の通いあいと悲劇的な結末は、もしセックス抜きだったとしても十分ひとを感動させえたであろう。むろん、性的関係を入れたことで格段に素晴しいものになっていたが。
ところで、十年以上前に東京レズビアン&ゲイ映画祭で上映されたこの映画に、仮に「肉体関係」なしの原作があったとして、そして、このような書きかえをした脚本家が女性だったとしたら、それは「やおい」と呼ばれるのだろうか?
こう考えると、やおいという概念の持つ差別性がよくわかる☆5。作者としてであれ読者/観客としてであれ、男性のホモエロティックな表象にアクセスする者が女であるとき、それは彼女(ある場合には作品)を、「亜種」「スタンダードならざるもの」「有徴」☆6と、つまりはあらかじめ信用失墜させられた二流の存在と決めつけようとするのだから。かつて塚本邦雄は、イエスと弟子たち、レオナルドと弟子たちの関係を素材にホモエロティックな小説を書き、あるいは、映画の中の男たちの関係を舐めるように深読みして書きつづったものだが、今ならあれも「腐女子の発想/妄想」と早合点されよう。
先日、ラジオ番組「ライムスター宇多丸のウィークエンドシャッフル」で、劇場公開中だった『アラビアのロレンス』完全版が取り上げられた際、「元・腐女子」の名で届いた次のような投稿が紹介された。
このような意見を公にするのははばかられるのですが、全篇にわたってほとんど男性しか出てこないこの作品、随所に萌えポイントがあるので、ラブやエロスでない関係性萌えのお好きな方にはおすすめです。
これに対し宇多丸は「ラブやエロスの萌えもある気がするんですけどね、エロスのね!」とすかさずフォロー、行き届いた解説を加え、「この映画、ほとんど、メインなところでは女の人出てこないんだけど、いやいやいや、出てるよロレンスが!」と断言していた。
ロレンスがそういうキャラであることはわかっている人には先(からおなじみであるが、「やおい文化」の可視化が進み、また同性愛差別は正しくないというそれなりの認識が多かれ少なかれ広まるにつれ、ホモエロティックな表象を前にしたとき、以前なら男性同性愛者が揶揄されたであろう状況で、「腐女子」に嘲笑が向けられるのを見るようになった。これは一つには女の方が非難しやすいからだが、彼女たち自身、自らの好むもの(好んで「妄想」と呼ばれ、それが現実に根を持たないことを強調する)が「一般人」には嫌悪の対象であることをわきまえるよう、自他ともにしむけるという傾向があり、それが「元・腐女子」の文面にも滲んでいたのを、宇多丸の、ホモフォビアのない男性ならではの痛快なパフォーマンスがあっさり吹き飛ばしてしまった。
なお、ロレンスのような、通常の男性性から逸脱した受け身でマゾヒスティックなキャラクター(映画表象としても伝記的人物としても)は、それ自体、やおいに親和性があるのだが、これについてはまた立ち戻ることになるだろう。
「この図書館にやおいはありますか?」
作品は物質の断片であって(たとえばある図書館の)書物の空間の一部を占める。「テクスト」はといえば、方法論的な場である。/「テクスト」は、ある作業、ある生産行為の中でしか経験されえない。したがって、「テクスト」が(たとえば図書館の書架に)とどまっていることはありえない。「テクスト」を構成する運動は、横断である(「テクスト」はとりわけ、作品を、いくつもの作品を横断することができる)。(強調は原著者)(「作品からテクストへ」、『物語の構造分析』)
大橋洋一が「ゲイ文学」について言っていることは、バルトが「テクスト」について言っていることとオーヴァーラップしよう。「ゲイ文学とは何かという問題は何をゲイ文学と認定するかを決定するゲイ文学に関する理論と関係する」と彼は言うのだ。ゲイ文学はゲットー化され可視化されたものの中にあるのではなく、「ゲイ文学の場合、理論が作品をマッピングする」(「ゲイ文学」、『岩波講座 文学 11 身体と性』)。
大橋のゲイ文学に対する非本質化は、やおいとは何かという問題に対しても有効であろう。だが、BLとしてレーベルされて売られているものに限って論じながらやおい一般について語ろうとする愚について批判するのは別の機会に回すとして、今は、昨年、大阪府堺市で、「書物の空間」から特定の「物質の断片」を追放することでやおいを排除しようとした蛮行について触れておきたい。
周知の通り、この事件では市立図書館の本棚から5499冊を撤去、「この種の図書」の購入、閲覧を中止し、該当図書は廃棄する方針であるという、市民からの投書への解答を市側が公式サイトに載せた。投書は、「女性向けの男性同性愛小説、いわゆるBL」には、男同士が抱き合い、キスしている表紙のものがあり、しかもそれを読むのが女性、これはセクハラで、子供への影響が心配と主張していた☆7。その後、決定は撤回され、BLは実際には150冊程だったこと、投書はフェミニズムに対するバックラッシャーのしわざであったことが判明している☆8。
投書の論理は支離滅裂とはいえ、ホモフォビアと女性の性欲に対するフォビアの典型的な特徴を示して興味深い。マジョリティの潜在的なホモフォビアに訴えんとしているのは明らかなのに、同性愛表現が悪いとは言明していない。同性愛者の人権に対する認識が限定的ながら広まりつつある今日、この投書ではホモフォビアのあからさまな表明は避けられ、代りに女性のセクシュアリティが攻撃対象とされた。ホモフォビアと「やおいの可視化」が衝突するとき、ホモフォビアはゲイ男性ではなく女性に向けられる。ホモエロティックな表象を、「腐女子の特殊な好み」として非正統化するのだ☆9。「セクハラ」について言うなら、男性のヘテロセクシュアルな欲望の表現に一方的にさらされることを拒否する根拠を女たちに与えたのが、環境型セクシュアル・ハラスメントという概念であった。この場合、いったい誰に対する「セクハラ」なのか。ここで「セクハラ」という語は、まさしく〈横奪〉的に使用されている。
そもそも、図書館に「男女が抱き合い、キス」している表紙の本があって、「それを読むのが男性」であったなら、こうした対応は考えにくい。ところが女の場合、そのセクシュアリティとは、管理され、〈善導〉されるべきもので、それが可能だと思われている。そして「子供への影響」。これは実のところ女が〈子供〉扱いされているのだ。それにしても「子供への影響」とは、かつては「頭の固いオバサン」(と同一視されたフェミニスト?)というステレオタイプが「ヒステリックに」言い立てることではなかったか。これまた「オバサン」のお株を奪う〈横奪〉、ほとんどパロディであった☆10。
もう一つ、これも昨年のことだが、日本記号学会の大会でBLをテーマにしたシンポジウムが開催された。そこで何が起こったかは複数のサイトで言及されているが、筆者が直接見聞きしたことではないのでこれはおくとして、その後、同学会の公式サイトに、実行委員長をつとめた男性の美学者の報告「何でもないことの幸せ」が載った。知らない対象について平気で思い入れたっぷりに書くのにも驚きだが(自分の専門領域についてだったら、まさかこんな安易なことはすまい)、これもまた、女にはふさわしからざる性的な過激さをセンセーショナルに言い立てる「堺市民」とは逆のベクトルながら、女の性欲を絶対見たくなく、あくまで「何でもないこと」として“否認”しようとする実例になっていた。
やおいを好む女性は、かつては「やおい少女」と呼ばれ、現実の恋愛や性行為を経験すればやおいから卒業してゆくものとされた。「少女」とは言いがたい年齢になっても、また、結婚後も、やおいを捨てない女たちが知られるようになってこの呼び名はすたれたが、現在でも、女性の真のセクシュアリティから何らかの原因で外れているため、男同士の性愛に「仮託」するのだという説明は後を絶たない。「仮託」の理由が、未熟さゆえの逃避や、現実の男性とでは対等な関係性を築けない状況(これは今でも人気のある見方)から、積極的な娯楽に変わろうと、この解釈のはらむ問題は本質的には変わっていないと思われるが、これについては次章で触れる。
「物質の断片」は撤去できても、エロティックな表象はテクスト同様、書棚にとどまってはいない。親がいくらある種の本を避けようと、子供とは、たとえば「おだいしさま」からさえ(あるいは、そこからこそ)刺戟を受ける、徹頭徹尾性的な存在なのだから。明示的なポルノグラフィであろうが、“一般”図書だろうが、本当は関係ない。女は「書物の空間の一部を占める」、それと名づけられたゲイ文学を読むだろうし、「明示的ヘテロ文学」を「ゲイ文学へと読み換える」(大橋)ことすらするだろう。これは、「ゲイとは無縁の文学すらもゲイの物語へと変換する光学を誇る」と大橋洋一が言うような「ゲイ理論」をマスターした結果ではない。それはこの社会における女の疎外の結果であり、こうした、病者ならぬ被疎外者の〈光学〉を身にそなえていたところで、彼女には何の誇りにもならなければ、得にもならない(楽しむことができるだけだ)。ともあれ、彼女は横断的に読むだろう。「書架にとどまって」いる本を隠したところではじまらない(むろん、堺市のこの行為は弾劾されるべきだが)。そして、女になぜ男同士のエロティシズムが好まれるかは、ジャンルBLばかりをいくらためつすがめつしたところでわかりはしないのだ。
2 やおいとその外部
ディレッタントからオタクへ
もちろん、時代のメンタリティという奴は、意識されているか否かにかかわらず、その時代の人間に染みついて付き纏い、寝ても起きても悪所に入っても食事をしても馬から落ちても、その一々に影響を及ぼさずにおかず、当然、当時の誰彼が書いたり描いたりしたものにも濃厚に反映するもの――ということになっているのだが
――佐藤亜紀『略奪美術館』
石田仁は『ユリイカ』が同じ年(2007年)に二度も出したやおい関係の特集のどちらにも論文を書いている。第一の論文で、彼は「リアルゲイ」という言葉を聞いて、現実のゲイの方が「有徴」に、「スタンダードならざるゲイ」にされてしまったことに衝撃を受けたと言う。「やおい/BL業界では、もはや「リアル」なゲイは参照の淵源ではなく、あえて形容詞をつける亜種であり、「リアルゲイ」は「私たち腐女子」の嗜好や萌えとは無関係という共通認識があるように感じられる」。しかしかつてはそうではなかったとして、石田は1988年から七年間の雑誌記事を追い、ゲイと女性の社会的身分の類似や連帯可能性が語られたといういわゆる“ゲイ・ブーム”の言説とその失速をあとづける。「やおい/BLは、つねに〈女〉としての自己とは微妙にずれた地点の表現を経由して快楽を手におさめてきた。しかしこの快楽を自律的に備給しているかのような語り口が成立したのは最近である」。
〈ゲイ・ブーム〉ドキュメントとしては労作であり、リファレンスとして有用であろうこれを読んでまず抱いた疑問は、そうした言説と当時のやおい作品がどう関連づけられうるのかということだ。やおいの「自律」がありえないのは自明である(そのことは前章で述べた)。新しく「やおい文化」に参入する若い女性の中には、〈完全に内的で唯官能的な欲動の「経験」〉(石田)として「萌え」を体験し、「歴史」を知らぬ者がいるかもしれない。だが、その「歴史」とは、たかだか二十年前の多分に際物的な言説のことであろうか。現在の「腐女子」の“無関心”に対して、「しかしたとえば「エロ絵巻」(超短篇エロ小説にイラストが添えられたやおい/BL作品)における話の筋の展開は、ゲイポルノのシナリオを、ほとんど忠実に模倣しているようにさえ思える」と石田は言うが、シナリオ(性的幻想)とルポルタージュ的雑誌記事(社会的関心)とは直結しない。ゲイに対する社会的、政治的(お望みなら心情的)共感が、「唯官能的な欲動」に通じることなどありえない。共感とはたとえば次のように起こる。
柏崎…あとおもしろいのは、柏崎にしても笹生にしても、ジョン・プレストンをお手本にしているんだよね。
笹生…お手本と言うか、同好の士、ですが。彼は実際に行為者でもあったろうけど、妄想は似てます。
木谷…わたしは一方で、プレストンが活動家であってポルノ作家でもある、というのが好きだな。さっき言った、ファンタジーと現実どちらも必要、というのを、ちゃんと一人で体現した人だよね。
柏崎…私の場合はプレストンを読んで、自分のファンタジーと同じなのに、すごくびっくりした。吹っ切れたのね。あ、なんだ、同じなんだ…って。ヘテロだろうが、ホモセクシャルだろうが、変わらないんだって。
柏崎玲央名・木谷麦子・笹尾撫子他の1996年の座談会「私たちはなぜ「やおい」に手を染めたのか」(『トーキングヘッズ叢書第8巻 松浦理英子とPセンスな愛の美学』)から取ったが、ここで小説家である二人(柏崎、笹生)は、ゲイポルノ作家プレストンへの性的共感を率直に語っている。「ヘテロだろうが、ホモセクシャルだろうが、変わらない」とは、性的ファンタジーはヘテロ/ホモという分割されたアイデンティティに還元されるものではないということである。欲望は横断するのだ。
ジョン・プレストンはゲイ・エロティック・ライティング(と彼自身は呼んだ)の代表的作家で、Flesh and the Word(1992)というアンソロジーで、ゲイ・エロティック・ライティングを一般読者の手に届くものにした人だ。ゲイポルノ・シリーズ「バッドボーイ」の邦訳が一時「女性向け」の「ラベンダー・ロマンス」として白夜書房から出て、プレストンも訳されていたから、柏崎らはこれを読んだと思われる。Flesh and the Wordはシリーズになり、男性名で書く女性作家の作品を集めた章を編んだり、女性がなぜゲイポルノを書くかが考察されたりもしていた。私自身はFlesh and the Wordを銀座の今は亡き「イエナ」で見つけてプレストンを知ったが、池袋西武「リブロ」地下フロアを洋書売場が占めていた頃はゲイ書籍コーナーも充実していた。あの当時もう少しきちんとゲイポルノが訳されていたら、BLの性描写も今よりましになっていたのではないか(ジャン・ジュネ以来、ゲイ作家の性描写の精妙さには定評がある)。
話を戻すと、「リアルゲイ」への腐女子の“無関心”に拘泥する石田は、たとえば「ファンタジーと現実どちらも必要」という木谷の言葉になら共感するのであろうか。「活動家であってポルノ作家でもある」ことがプレストンにできたのは、男であり、かつゲイ・エロティック・ファンタジーを持つという、ゆらぎもねじれもない(少なくとも外的には)身分だったからである。性的ファンタジーの必要すら認められていない女にとって、それは“身分不相応”なことだ。自らにとってこの上なく重要であることだけは確信できるものをどこまでも他人事(とされてしまう不快さに堪えながら、腐女子は「リアルゲイ」から距離を置こうとする。そもそも「リアル」と呼ぶのは「有徴化」ではなく、「私たちのは本物ではありません、作り物です」と、男(であるゲイ)にへりくだってのことだ。上記座談会で笹生は、「読む人は誰でもいい。わたくしはSMポルノ作家で、多分にファンタジーを書いています。だれでも、似た趣味や感性の人がおもしろがってくれればそれでいいです」とつつましく語っている。
第二の疑問は、第一とも関連するが、やおいと外部の関係を言うなら、なぜ、当時のやおい少女の視界にあったはずの、徒花(記事以外のゲイ表象を参照しないのかということだ。95年には女性たちによる『ゲイ文学・耽美小説ブックガイド』(白夜書房)も出ている。過去のハイ・カルチャーの中に潜在的・顕在的に「ゲイ文学」は存在し、やおいを愛好する女性たちもそれで育ってきたのであるから。
この時期、少女マンガの世界において、「耽美」「幻想」「退廃」「世紀末」「少年愛」といった美学が、背伸びした文学少女たちの愛玩物として一般化してゆく。(浅羽通明『澁澤龍彦の時代』)
結果としてこうした〈美学〉を「少女たち」に広める一人にもなった澁澤龍彦について、浅羽通明はこう書いている。「この時期」とは、澁澤が〈選ばれた少数者〉のものであることを止めつつあった七十年代中葉を指すが、ひとことで言えば、それは、かつては高雅な趣味を持つディレッタントだったものが、オタクに置き換えられていった時期である(やおい的なものの大衆化、資本と結びついた商品化ともこれは関連する)。アマトゥール(アマチュアでなく「愛する者」)と澁澤は自身を呼んだが、ディレッタントにしてアマトゥールとは、彼が訳した『さかしま』の主人公(十九世紀末の高級 引きこもり)の自己規定でもあった。
浅羽も引いているが、澁澤と学問的研究との違いについては、『ユリイカ』の澁澤追悼号で若桑みどりが印象的な文章を書いていた。「澁澤龍彦が「……である」と書く時に、我々は、「……とだれそれは、どこそこで述べている」と書く。そして注をつけるのである」(「注のある文章について」)。検証可能性を持たない澁澤の文章は「芸術作品」であって「研究」ではないと若桑は言う。
若桑の言葉は澁澤の気に入るだろう。何にせよ澁澤に「教養」(とセンス)はあったのだ。文学研究に限ってみても、理系論文の検証可能性とは根本的に違う以上、検証可能性と呼ばれるものが単なる形式に堕しているのはしばしば目にするところだ。「芸術作品」と「研究」の違いに安住できるのは澁澤であり、間違っても「研究者」ではない。若桑みどりのような書き手であってはじめて、自分の書くものは澁澤のような「芸術作品」ではなく「研究」に過ぎないと謙遜することができるのである。スタイルとレトリックは内容と不可分であり、それらのなさをリファレンスでカバーすることはできない。
澁澤が黒ビロードで装幀した持ち重りのする本を出していた頃、そのページを繰る手は限られていた。現在では皮肉なことに、検証可能であるかの見かけを持った「研究者」の論文は、実のところお話にならないレヴェルだったとしても、時に大きな影響を及ぼす。にもかかわらず、大衆化社会において相対的に地位の下がったアカデミズムの中の彼らは自らの権力性に無自覚だ。これについては最後にまた触れることになろう。
■註
☆1 表題は〈あたしはレズビアンだと思われてもいいのよ〉というブログ・タイトルから拝借した。ちなみに、同ブログの管理人の心意気はこうである――「レズビアンという汚名も引き受けましょうということです」。
☆2 石田仁の論文では同じ語が〈横奪〉とされている。筆者は通常「流用」を使用しているが、本稿では〈横奪〉をも〈流用〉することになるだろう。
☆3 「身を挺している」とは、『仮面の告白』で三島由紀夫が語り手に、幼少時、汚穢屋や神輿担ぎの若者が体現していると感じ、魅惑されたと言わせている概念。
☆4 これらは家族愛を除けばほとんどすべて男にだけ開かれている――少く
とも、伝統的に男同士である場合にもっとも魅力的なものとして表象されてきた――社会関係である。昨年、女性に今「戦国武将」が人気という話題がラジオで取り上げられた際、腑に落ちない様子だった年配の男性司会者は、ドラマやゲームで武将が〈イケメン〉に描かれていると聞いて頷き(異性愛的な理解)、「友情や主従関係が魅力」と言われて、「友情に憧れるのね」と納得していた(ホモソーシャルな理解)。「主従関係」(位階的な関係)がなぜ魅力なのかを不思議には思わなかったようだ。
☆5 むろん、「やおい」という概念を捨てよということではない。女性であることに問題はないが、意味はあるのだから。
☆6 石田仁によって、腐女子に「リアルゲイ」と呼ばれた結果、現実のゲイが担わされるものとして提示された概念の流用。
☆7 堺市ホームページ。
☆8 細かい経緯はウェブサイト「みどりの一期一会」に詳しい。
☆9 すでにログが流れているが、「フェミナチ監視掲示板」と呼ぶウェブ掲示板で、実際に投書を送る以前の臆面もなくホモフォビックな書き込み(「とにかく、BLは、「ホモ」の「ふしだらなワイセツ行為」を「露骨」に描いた「不道徳」極まりない「有害図書」だから、先ずは早急に人目につきにくい場所に配置替えしてもらいたい! と言うべきでしょう。」)や、BLをフェミニズムの陰謀視する説が読めた。
☆10 男の場合、こうした抑圧が考えられない(性犯罪に直結する場合を除き)もう一つの理由は、女と違って、性欲の現実離れ――本質的に想像力に基づくものであること――が認められているからである。
★プロフィール★
鈴木薫(すずき・かおる)今号には、本来なら当然「〈ホモソーシャルな欲望〉再考」の続きが載るはずでした。それから、本誌編集人の黒猫氏に石田美紀氏の『密やかな教育 やおい・ボーイズラブ前史』の書評を書かないかと言われて引き受け、うっかり両方書くつもりになっていました(汗)。そして、書評だけは
ともかく仕上げなければと思い続ける(書き続ける、ではない)日々。最後に突然、しばらく前に書いたものの、行き場を無くした(この間の事情はいずれ書くかもしれません)テクストに大幅加筆したこれに替わりました。後半は確実に次回に。書評も次回あらためて書きます(両方書くつもりになっている……)。で、「〈ホモソーシャルな欲望〉再考」(2)はその次に。
Web評論誌「コーラ」07号(2009.04.15)
「新・映画館の日々」第7回:〈あたしは腐女子(だと思われてもいいのよ〉――男性のホモエロティックな表象と女性主体(上)(鈴木 薫)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2009 All Rights Reserved.