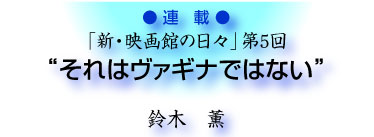|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
以下は、2002年12月22日、「セクシュアリティ研究会」と呼ぶ集まりで発表した際配付したレジュメに、もとになったノートを参照して加筆したものである。 この年8月の同研究会の初めての会合では、守如子さんが“レディースコミック”について発表している。レジュメを見ると、ポルノグラフィが一般的に女性にとっては受け入れ難いという前提の上で、その女性にさえ受け入れられるようなポルノグラフィとはどういうものかという話の運びになっていた。ポルノとエロチカの区別はきっぱり廃しているものの、そこから説き起こさないと納得されまいという配慮があったのだろう。たった六年前の話である。 見なれない顔(私や友人)を見て、守さんはポルノ反対のフェミニストが来たかと思ったという。 そのときの守さんの発表から触発されたものは、拙稿の2章(「ヘテロセクシュアル女性は男性表象の夢を見るか」)に跡を残している。 当時はまだ“腐女子”が注目されることもバッシングを受けることもほとんどなく、あまり外野にわずらわされずに、最近書いたものに比較すると理論的・原理的なことをやっている。 あらためて読み返すと、かなり「やおいのひみつ」の核心に迫っているかと思われるが……一方では、現在ならこういう書き方はすまいというところもあるけれど、やおいについての議論が盛んになっている今、当時のままお目にかけることにもいささかの意義があるかと思い、加筆・訂正は意味が通りやすくするための最小限にとどめた。なお、太字による強調はすべて鈴木による。 やおい的身体――それはヴァギナではない Female identification with a certain kind of male subjectivity 1 はじめに ――そして、女が「男×男」を愛するとき 女性が読む男性同性愛小説 女性が目ざす男性同性愛物語 (以上、藤本純子) 女性の男色嗜好について 女性の少年愛嗜好について (以上、谷川たまゑ) これらの演題/論文はタイトルがおかしい――私のサブタイトルも。 やおいは「倒錯」である。倒錯とは、カジャ・シルヴァーマンの定義によれば「制度がよって立つ二分法の不適切な配備、ないしは否定」のこと。 (上記タイトルは「不適切な配置」だったのだ。) ホモセクシュアリティもトランスセクシュアリティも、「受け入れられている考え」によれば二分法からはみ出ていない。 「女が男色嗜好」の異様さはきわだつ。 サブタイトルにあるa certain kind of male subjectivity という文句の出典はシルヴァーマンで、これはひとことで言えばファリックでない男性主体のことだ。 今回の発表では、「男×男」の右側の男をそのような主体と見なして、その「男」への女性による同一化について考察する。 それはどんなsubjectivityか?
これはカジャ・シルヴァーマンの“Male Subjectivity at the Margins”の一節だが、性的差異を無効にする、そのようなmale subjectivityへの女性の identificationという逸脱をめぐる私たちの探求もまた、人が「現実」と思っていることへの挑戦になろう。 「やおい」が非難(あるいは軽視、あるいは嘲笑)されるのは、まさに、女でありながら男に同一化するという、このねじれ、cross-identificationゆえである。 もう何年も前になるが、アメリカのゲイ・アダルト・フィクション「バッドボーイ・ブックス」の何冊かが訳され、少女マンガ風のイラストレーションの表紙と「ラベンダーロマンス」の名を付けられて「耽美」コーナーで売られるという「やおい化」が起こったことがある。この場合、やおいについてしばしば見られる、女性によって女性のために書かれた云々という定義はあてはまらない。アメリカの「ゲイ・エロティック・ライティング」には優れた女性の作家もいるが、言うまでもなくそうした書き物は「女性向け」ではありえない。 「やおい」という言葉は明らかに「差別的」だ。ある種のテクストにアクセス(読む/書く)する者を性別で分け、あたかもそうした個体が女性であることが問題であるかのような含意を生じさせているのだから。 といっても、アクセスするものが女性であることを気づかせるのは必要なことでもある。女性であることに非難されるべき点はないが、意味はあるからだ。 たとえば……マルグリット・ユルスナルはやおいか? ドミニック・フェルナンデスはユルスナルの『ハドリアヌスの生涯』を、作家の性別を一顧だにすることなくひたすら男性同性愛――ローマ皇帝に対してこの名を適用することはアナクロニズムだが――の表象として論じていた。むろんそれは完全に正しい。しかし……レズビアンであったユルスナルがついに同性を自らの分身として描かなかったことに意味がないわけはない(むろん、ローマ皇帝にも放浪の錬金術師にも女がなれようはずはないのだが)。 あるいは……男名前でパスしていたSF作家ジェイムズ・ティプトリーJrが女だとわかったとき何が起こったか。男でなければ書けないと「賞賛」されていたその作品への見方が変わり、たとえばフェミニズム的、ジェンダー論的に、また〈抵抗〉として読まれるようになったのだ。 男性作者の場合も同様だ。たとえば塚本邦雄。愛し合う男たちはつねに高貴で美しく悲劇的であり、彼らを追いつめる醜悪な現実を女が象徴する、限りなくミソジニックな物語をやおいとして読むこと。いや、女性が読むことで、それはすでにやおい化されているのだ。さわるとさわったものが黄金になる王の指のように、女が触れるとそれがやおいになる。 ただし、ミダス王の場合とは反対に、女が触ることによって、純金のmasculinityと信じられていたものが変質(denature)し、別の相貌を見せてくるだろう。 2 ヘテロセクシュアル女性は男性表象の夢を見るか? 男の子が「エロマンガ」によって異性間性交専門の主体に鍛え上げられのはわかる。しかし、女の子の場合はどうなのか? ヘテロセクシュアルな女性主体はけっして自明なものとしては存在しない。 男性同性愛を扱った映画に女性観客が集まる現象について、あるゲイ男性は「女性とゲイは性的指向が同じだから」と(好意的に)コメントしていた。 だが、性的指向では切れない。「性的指向」とは対象選択に基づく区分であるが、たとえば「レディースコミック」において視界の中心に置かれるのは男性表象ではなく、ナルシシズム的な同一化の対象としての女性表象なのだから。 欲望されるべき存在としてディスプレイされるのは女性であり、女性読者は女性表象に同一化して女性のポジションをとり、愛される女としてセックスを享受する。これはフロイトの言う女性に対する「性的過大評価」(通常のヘテロセクシュアル男性がしていること――女性にペニスがないにもかかわらず/ゆえに)の受け入れであり、女性とその快楽へのナルシシズム的同一化であり、女性のセクシュアリティとしては、順当で、正統的で、社会から承認されうるものだ。 一般的に女の子は、人々の視線を惹きつけるスペルタクルとしての女性に同一化することによって女性として「主体化」される。よく、女が化粧するのは男に見せるためではなく自分のためだと言われるが、しかし、ナルシシズム的同一化こそが異性愛女性のセクシュアリティを特徴づけるものだとしたら、これは異性愛機構の中での女性のポジションそのものだろう。こうした意味で「レディースコミック」は、男性を(ヘテロ) 「レディースコミック」は「女性向け」である。これは「やおい」と違い、文化の中に席を持っていることを意味する。異性愛の枠内にとどまっている限り(いや、レズビアン描写があろうと)、それは文化の中の「女」のポジションに安全に回収されうる(女には「淫らな女」というポジションもある)。 「レディースコミック」に対する苦情が先月の読売新聞の投書欄にあった。「過激な性描写のある」それを中学生の女の子が立ち読みしているのを注意しなかったとコンビニの店員を非難している投書者の心配は、なんと「援助交際の低年齢化」だった。 かくも異性間性交に特化され、女の性的ファンタジーを認めまいとする文化の中に「女がホモの話を好む」ことの居場所はない。適切にジェンダー化されなかった女は、主体としてのステイタスを失ったアブジェクトに身を落すしかない(先手を打って、彼女らは自ら「腐女子」と称する)。 エロティックな男性表象は誰のためのものか? ゲイ男性のためのものであるとき、それは「倒錯」ではない。 3 それは異性間性交ではない
後半部の、やおいとの著しい類似に注目されたい。 フロイトはいかにも彼らしく、近親相姦の回避というエディプス的解釈のみをしている。男性の場合、笞を握る者を父親から母親に変えたことで「同性愛を免れた」と言うのだ。一方、「女児の場合は、自分で自分の性を放棄し、全体的により徹底的な抑圧作業を行なっているが、それでも父親を手放すことはできず、自分を叩かせることは思い切れないでいる。そして女児は自分が男の子になっているので、主として男の子たちが叩かれるように仕組むのである」 上記解釈に見られる、異性間性交中心主義によるゆがみ――くだんのbeating fantasyをヘテロセクシュアルな近親姦願望の偽装であるとして、男が男に打たれる(愛される)表象であることをかえりみないフロイトは、まるである種のやおい論者のように、これは男性同性愛に仮託したファンタジーにすぎないと言っているのだ。 カジャ・シルヴァーマンはこの論文について次のように述べる。
「この、女性が占めることはほとんど考えることもできない」subject-positionを女が占めるという「女らしくない」事態に直面し、その弁明をしようと考える人、「私が女性である」ことと「それが男性同性愛である」ことの倒錯的なねじれを解決しようとする人の多くが、「それは男性同性愛ではない」というステイトメントをする(註1)。 谷川たまゑの先駆的論文は、上記の「倒錯」を、メタファーであり、「男色嗜好を持つ女性」自身の問題の解決法であるものとしてとらえ、24年組を中心とした少女マンガにおける「少年愛」とは、女性の母親との関係(特に前エディプス的母親との関係)を解決する試みであると主張した。 「隠喩で語られた世界とは、通常の父性的な言葉の世界では、嘘や幻想や否定的なもの、時には非在そのものを意味する」 「嘘を、非在を、否定性を受け入れるという負荷に耐えてもう一つの真空の世界であるファンタジーの領域に足を踏み入れるか、否定性を否定して自己を失うかということであろう」 彼女は、「私の王国は地上のものではない」と言っているかのようだ。そのために、現実性という高い代価を支払っている。続く論文で、谷川は「やおいシミュレーション説」――男同士という自分とは関係ない装置による、男女関係の模倣実験であるとする――に当然ながら反対している。しかし、むしろ一般的には、やおいは、そのような、男同士に仮託した、ヘテロセクシュアル女性のファンタジーとして解釈されることが多い。 「ジェンダーレス・ワールドの愛の実験」とかつて上野千鶴子は呼んだ。現実の異性愛の世界は制約に満ちていて女にとって満足のいかないものなので、それが取り払われた世界での可能性を模索しているのだという“理解”である。「最近の」ヴァージョンとして次のような例がある。
この論文は紙幅の関係で縮めたそうで、全長版では、この部分は次のようになっている。
ミソジニーから自由になるため、男同士の物語に仮託している? そんなことはあるまい。男同士の物語があまりにも魅力的であり、それが女を悪者として描き、女を徹底的に排除しているからミソジニーに陥るのだ。 これらの文章は、上野同様、「それが異性間性交ではない」ことの魅惑を感じることのない者により、谷川のような切実さもないまま、「差別構造」の解消が「すべて」を変えうる、そしてそのときにはやむをえない「仮託」も終るという考えのもとに書かれている。「男になりたい」というFTMトランスセクシュアルに、「あなたの気持ちはわかる。女のジェンダーが嫌なのね。私だってなりたいわ、そうすれば差別と無縁になれるもの」と言っているようなものだ。 再び作り直されるまでは異性愛は悪だから、それまでは「男同士のカップリング」は「ノンケ女性」の夢の託し場所であり、代用品? これらはいわば「異性愛改良主義」であり、「異性愛の再発明 reinvention」への期待の中にやおいを回収しようとするものだ。(いうまでもなく、表象されていたはずの「同性愛」はホモフォビックにも抹消される。) 谷川の、現実の同性愛には関係のない、ある種の人々にとってはどうしても必要な「メタファー」なのだという言い分は、しかし、次のような、ファンタジーが現実に影響を与えている、ゲイについての誤ったイメージを広めているという非難から逃れうるものではない。
しかし、「やおいが現実社会から隔絶した真空に存在しているわけでない以上」、そのファンタジーは「(ノンケ)女性の(ノンケ)ファンタジー」という混じり物のない本質ではありえない。逆に、いかに「非在に」耐えて「もう一つの真空の世界であるファンタジーの領域に足を踏み入れ」ているのだと谷川が主張しようと、ファンタジーはすみからすみまで社会的なものである。 溝口は、「オレはホモじゃない」という科白を使った「やおいテキスト」をホモフォビックと断じた上で、あえてその名で呼ばれるゲイ・キャラクターたちの登場する作品を、「ホモフォビアの装置ではない」とあっけにとられる単純さで分類している(註2)。 しかし、内容的な「正しさ」とは、実は書き手の知識によって乗り越えられる相対的な距離である。乗り越えられない距離は「彼女が女である」ことと「それが男性同性愛である」ことのあいだにあり、また、「男性同性愛の表象」と「女性同性愛の表象」のあいだにある(註3)。
4 「お前の愛は素晴しかった、女の愛にもまさっていた」 溝口はどうしてやおいでは男同士が〈攻め〉と〈受け〉に分かれ、「固定された男女のジェンダー役割を演じるのか」と問い、やおい作品は「主人公たちの恋愛をドラマチックにしたてるための小道具として同性愛を利用している」にすぎず、男女間の性交を、そのまま男同士の関係に持ち込んでいるのだと述べている。 こうした主張には、少なくとも二つの問題点が指摘できる。一つは、その記憶喪失ぶりである。ジャン・ジュネを、気軽に侵犯を行なうが一つの二項対立から脱したと思うとたちまち別の二項対立に陥るとロラン・バルトが書いている[気軽に男同士で性行為をするが、男女という二項対立から脱した途端に「固定された」男役女役にこだわるという意味]アラブ人を、人は忘れてしまったのだろうか。もう一つは、そのホモフォビックぶりだ。同性愛は抹消され、すべては異性間性交に還元されてしまう。そこにあることが男性の表象であることはもはや一顧だにされない。もちろん、「最近のやおいテキスト」の作者が、「伝統」に基づいて「セメ/ウケ」を設定したというより、直接的には「テキスト」が「テキスト」を産んだという方がずっとありそうなことだ。 それでもなお、そこにあるのは男性の表象であって、ヘテロセクシュアリティに還元することはできない。 なぜなら、男の表象であることには快楽がかかっているからだ。 三つの物語伝統[アキレスとパトロクロス、ギルガメシュとエンキドゥ、ダビテとヨナタンの三つの物語]のすべては、二人の、二人だけの人物のあいだの親密な友情を特色としている。この二人の人物はつねに男性である。彼らは対を形づくるが、比較的二人だけで孤立している。(…)さらにこの関係は、〈…〉つねにその焦点が外側に向けられていて、栄誉ある行いの完遂とか、政治的目的の達成とかいった。その関係を超えて活動している目的を備えている。〈…〉英雄的友情はたんに二者関係であるだけではなく、位階的でもある。それは(アメリカのラジオやテレビの昔の聴視者には、ローン・レンジャーとトントの例からしておなじみの)仲間で、従僕で、親友のいる英雄の型を示しているのである。(デイヴィッド・M・ハルプリン「英雄とその親友」) ハルプリンは、その愛が「女の愛よりまさっていた」と死せる友を讃えるダビデは、ヨナタンが彼を性的に愛したと言っているのではなく、非性的な愛が性的な愛にまさるという不思議を言っているのだと述べている。しかし、ダビデとヨナタンの物語の成立より後代の古典期アテナイ人は私たちと同様に「理解」したし、また、アキレウスとパトロクロスではどっちが「少年」の役をつとめたのかと、(まるで「男×男」カップルの「セメ/ウケ」の別にこだわるやおい少女のように)決めようとして困難にぶつかった。 なぜなら、『イーリアス』成立の時代の男性カップルは、ギルガメシュとエンキドゥ、ダビテとヨナタンのケースに近く、古典期アテナイ人の知っているカテゴリー(「セメ/ウケ」だ)に彼らをあてはめるのはアナクロニズムだったからだとハルプリンは言う。(男二人がセックスをするとき彼ら二人をまとめて入れるカテゴリーを持っていなかったアテナイ人を、私たちが同性愛者と呼ぶとしたらそれもアナクロニズムであるように。) 「究極のカップル神話」は、何もヘテロセクシュアル女性の十八番ではない。しかもこれは、対等ではなく位階的、要するにヒエラルキーのある関係である(ヘテロセクシュアリティの位階的男女関係がオリジナルで、「やおい」がそれを引用しているのではない)。さらに、彼らの関係は恋愛だけでは完結せず、ともに何かに身を捧げ、(三島由紀夫の言葉を借りれば)「身を挺して」いる。男だけにしか可能でない関係というイデオロギーに染められてもいる。これは、性的関係の有無にかかわらず、今日ではホモソーシャリティとして私たちのよく知っているものだ。 ホモソーシャリティの表象(「お前の愛は素晴しかった」)は、私たちの社会をエロティックに満たしている。「映画に見る基本的なバディ関係とは、男同士の同性愛を軽蔑しながら、自分にとってもっとも真正で尊い感情は男と男のそれだと知っている、というものである。ここには、女性及び女性的な物事が単に嫌いという以上の女性嫌悪[ミソジニー]がある」と、ヴィト・ルッソは『セルロイド・クローゼット』で言っている。「自分にとってもっとも真正で尊い感情は男と男のそれだと知って」いさえすれば、実はこうした関係にとって、ダビデとヨナタンが現実に寝たかどうかなどは瑣末事なのだ。 むろん、ドミナントな男性主体にとっては、これは瑣末事どころではありえない。しかし、彼らと違って女性にとって、そのエロティシズムを見抜くことはなんら禁忌ではないので、女性はそれを しかし、言うまでもなく、女性にはまた別の問題がある。「女性及び女性的な物事が単に嫌いという以上のミソジニー」――女性にとってそれは自らを否定することなのに、彼女は自分の抑圧者に、自らを軽蔑し排除する当のものに魅惑され、同一化してしまうわけだから。 このような女性主体の位置は、レオ・ベルサーニが「直腸は墓場か」で、ゲイ男性が自らの抑圧者を愛してしまうことについて、自らを否定するマッチョな「男性性の表象を理想化し、それに劣等感をもってしまう危険」について書いていることによく似ている。ベルサーニは、「抑圧的メンタリティの内面化は男性の同性愛的欲望そのものの一部を構成している」と言っているが、このような女性主体もまた、「抑圧的メンタリティ」を「内面化」し、それが「彼女の性的欲望そのものの一部を構成している」と言えよう(註5)。 5 「私が彼になりたい」――エロティックな同一化の対象 「私が彼になりたい」――『仮面の告白』の語り手の幼い日のこの「ひりつくような欲望」は、「男×女」の場合通常考えられない。ナルシシズム的同一化は女性と同性愛者に割り当てられている。 男の欲望の対象となるスペクタクルとしての女性イメージに同一化すること(=女のポジションをとること)はエロティックな同一化と言える。一般に女の子は女性のポジションをとるよう、女性に同一化し、女性として主体化するよう、繰り返し呼びかけられる。 しかし、女性性へと誘惑されるのは女ばかりではない。男も誘惑されるのだが、しかしそれは同じ誘惑ではない。女性には自らの避け難い女性性を受け入れよという命令が下されつづけるが、男の場合はその逆で、生物学的宿命でもないのに女のポジションをとることは最大の禁忌であるからだ。 フロイトは、女性のペニス羨望に当たる男性の側の“対応物”として、「父に対する女性的態度の拒否」を挙げた。悪名高い前者だが、ジェシカ・ベンジャミンは、これを父とのホモソーシャルなつながりから排除されて母のポジションに身を落すことに対する抗議として解釈している。女の子は、父と自分を同一視すること、父のバディであることを拒否されて、他の男に対して女のポジションをとるよう強制されるのだ。 アンドレア・ドウォーキンが抗議しているのは女が女のポジションをとることが自然とされていることだが、私の見るところ、この強制の最大の弊害は、(女性自身にとっての)女性のエロス的価値の低下である。ドウォーキンは彼女が不適切と考えるポルノグラフィーをしばしば引用しているが、その中には、男が「女のように」犯されるゲイポルノが含まれている。ドウォーキンの意図は言うまでもなく(女が本質的にウケであることを含意する)「女のように」という比喩を非難することであるが、私はそこからはずれて、ここのポイントは「男なのに」というところにあると思う。「男でありながら女にされる」ことこそがエロティックなのだ。 一般には、女性の身体こそがエロティックな源泉であり、深い享楽を得ることができると想定されている。しかし、ある種の人々にとっては違う。女であることは醒めさせる。男であるという前提がなければ身体はエロス化されない。『仮面の告白』の語り手は、ジャンヌ・ダルクが女であっては「身を挺している」というあの感じは失われ、「ひりつくようなあの欲望」(同一化の欲望)の対象にはならないと主張する。享楽するためには男でなければならない。男であるものだけが女に身を落すことができ、「女の」快楽を味わうことができるのだ。 (誤って)それが女性の本質とされたために、女性は「ウケ」であることを楽しめなくなった。この結果、ある種の女性たちは、ホモソーシャル/ホモエロティックな関係の中で受動的な男性に同一化する方が、女性に同一化するよりはるかに受動性の快感が増すことを発見した。疎外された「ウケ性」を回復するためには、男の表象が必要であり、それに同一化することが必要なのだ。 「子供が打たれています」において、女の子は父に打たれる(愛される)ことをあきらめ、ファンタジーの中で男の子が打たれるのを見る観客になる。少年の身体を通して、受け身であることは賞翫される。 こうして、スペクタクルの中心に男性の身体が置かれることになる。異性愛の機構においては、けっして中心になることも注視されることもなく、愛される対象にもならないものが、今、エロティックな同一化の対象として横たわる。 これは女性にとってクリティカルな瞬間である。それはミソジニスティックな危機である。男性の表象が侵害され、その価値を下げられるのではない。むしろ、犯されるだけの価値のあるものとしてますますそのintegrityを高めるのだ。 一方、(ドウォーキンの言葉を借りれば)犯されて当然とされる女性身体は、ますます価値のないものになり、周辺化される。スペクタクルにもならなければ、おとしめられる価値さえ持たない。 6 〈 やおいは、ゲイ男性の誤った表象を流通させるという理由でしばしば非難されてきた。女性の表象を男たちがさんざんポルノグラフィックに消費してきたと同じことを、女がゲイ男性に対してやるのかというのである。最後に、一見対称的なこの二つのことが、どのように異なっているかを検討したい。 まず、権力関係が違う。だが、それだけではない。 たとえば「オリエンタリズム」……。西洋が東洋を正しく表象しさえすればそれでいいのだろうか? 大橋洋一によれば、問題は西洋が、オリエントが実は西洋であることを拒否することだという。これを私たちのトピックにあてはめてみるなら、男が女を表象する際には、女が実は男であることを拒否しているのだと考えることができる。 女について正しい表象をせよと要求することが問題なのではない。間違った表象によってではなく、女とのあいだに、その向うを完全に異質な他者とする境界を設定していることによって、それは批判されるべきである。女を絶対的な他者とすることで、女ではない、女と混じり合わないアイデンティティを男は確保する。 では、やおいで男を表象する女は何をしているのか。彼女は、男が女であることを拒否するどころか、進んで女にしているのだ(やおいにおける肛門性交を異性間性交の偽装と見なすのは、この事実をやわらげ、隠蔽しようとすることだ)。男が女を表象することによってしていることとは反対に、これは境界を無効にすることである。 ゲイのポルノビデオにおいては、ゲイ男性にノンケの男がレイプされるという設定が好まれるものの一つだという。スペクタクルの中心はゲイではなくノンケの男。ゲイ男性はどちらに同一化して見るのだろう? 襲う男か犯される男か。(もし後者だったら、ゲイとしての主体を確立しなくてはいけないのにノンケに同一化していると悩むのだろうか。まさか。)この場合、ノンケ男性はゲイよりも純粋に男性性を体現しているがゆえに、なおさらエロティックな価値がある(犯されるにふさわしい)ということだろう。「直腸は墓場か」のレオ・ベルサーニによれば、ゲイ男性は社会の中で自分を抑圧している当のものである男性性に魅惑され、ほうっておけば敵に、自分の抑圧者に加担してしまうのだが、その同一化が粉砕される場こそが直腸であるという。 ベルサーニの論文について論じつつ、カジャ・シルヴァーマンは、男性同性愛の古典的な定義「男性の身体の中にいる女性の魂」を、「女性の身体の中にいる男性の魂」へと――あるいは、a male psyche put at risk by its pleasurable relation to the vagina/anus へと――逆転させている。 (中野冬美は男性の表象によって自己を否定しているのだと自分を責めていた[註4参照]。だが、そのmale psycheが、ただ、否定され、(喜ばしく)粉砕されるためのものだとしたら?) だから、やおいの性交場面において挿入が行なわれる場所、それはけっしてヴァギナではない 。つまり、男性器によって侵入されるのが当然とされ、異性間性交、妊娠、出産へ、女性の従属的な立場――かつては「解剖学的宿命」と見なされた――へと自然につながる器官ではありえない。 代補/蛇足その1 ジュディス・バトラーは『ジェンダー・トラブル』の註の一つで、モニック・ウィティッグが講演終了後に聴衆から受けた質問、“Do you have a vagina?”に対し、ノーと答えた逸話を紹介している。女とは男との関係によって規定された階級であるがゆえにレズビアンは女ではないと言い、女体という男たちの幻想にまみれた言葉をレズビアン・ボディという言葉で置きかえた人は、それはヴァギナではないと答えたわけだ。 だから、ヴァギナもまたけっしてヴァギナではない 。それを持つ身体がレズビアンであろうとなかろうと。 代補/蛇足その2 vagina/anus――松浦理英子の『ナチュラル・ウーマン』はこの左の項から右の項へ、つまり汚されていないanusへ移ることで、「幻想にまみれた女体」の問題を処理(あるいは回避)したのだと言えよう。では、vaginaはどうなったのか。ヴァギナでないヴァギナは。人が到達できるのは描かれたvagina、「明確に規定された象徴的な現実のうちに位置づけられた」(ジジェク)それにすぎず、そして絵の下には「これはヴァギナではない 」と書かれている。lesbian vaginaの経験することはまだ表象されておらず、文化の中に登録されていない(少なくとも、エロティックな同一化の熱烈な対象になるまでには表象されていない)。レズビアンは現実に不可視である以前に、表象として不可視である。それが、レズビアン表象が男性のホモソーシャル/ホモセクシュアルな表象のようにはアクセスされることがない理由であろう。 ★註★ 1 もう一つの方法は「私は女ではない」と主張することである(論理的に言って)。描かれているのは同性愛ではない何ものかだという主張の対極にあるこの立場が、自分は当事者でありFTMトランスセクシュアル・ゲイだと主張するやおい作家、榊原史保美の場合であろう(『やおい幻論』夏目書房 1998)。これは説得力のある主張である。榊原の言うようにやおい愛好者の多くが存在論的にFTMゲイだとは私は思わないが、少なくとも榊原自身は、自らのゲイ男性への深刻なアイデンティフィケーションをそう表現するのだ。自分に関係のない事柄に(当事者でもないのに)かかわっているという非難に対して抗議する立場の、これは極北と言えよう。(ただし榊原は、自分が現実のゲイを描いているとは言っていない。) 2 溝口は、「俺はホモじゃない」という、研究対象にした「最近のやおいフィクション」に頻出するという科白を「ホモフォビック」と呼び、ある座談会で(やおいを読んでいてそれに出会うと)「『女のホモセクシュアル』だというアイデンティティ」を持つ自分は「『アタシは女のホモなんですけど、読んでて、いちいち、疎外感があるんですけど』と思っちゃって」云々と述べている。また、自分が論文で「護符のように出て来る」この文句を「ホモフォビック」だと批判したのは、何よりもその言葉によって自分自身が疎外感を覚えたからなのに、それを、「男性ゲイの側に立って、彼らのために、やおいにおけるホモフォビアを非難している」と、「一部に誤解された」という(『YAOIの法則』所収)。溝口は、「ホモ」の中にレズビアンが入っていると思っていたらしい。ホモフォビックという科白の解釈自体にも問題があるが、それ以前に、やおいのミソジニーに対してあまりにも鈍感であると言わねばならない。なぜなら、やおい読者にとってレズビアンは「ホモ」ではなく、「女」でしかないからだ。やおいの中では現実のゲイ男性が十分考慮されていないかもしれないが、それ以上に、レズビアンの、というより、女性の存在が考慮されていない。レズビアンであっても「名誉男」にはなれない。「女のホモ」以前に「女」が疎外されていることの深刻さを素通りして、ホモフォビアの内面化を言い立てたのでは、ゲイ男性の代弁者となって非難していると“誤解”されたとしても仕方がないのではないか。「女のホモ」など想定されていない。多くのやおい少女にとって、「レズ」は「ホモ」でなく「女」であるために、彼女たちのファンタジーを担い得ない。たとえ、やおい作品の中で政治的にも生理的にも「正しく」描かれたゲイ男性に「俺はゲイだ」と発言させたとしても、また、溝口の言うように「最近の」やおい作品には脇役として「クィアなレズビアン」が登場する例が見られたとしても、この基本的条件はゆるがない。榊原のやおい少女FTM説を溝口はナンセンス扱いしているが、しかしこれはこの自己否定の論理的帰結であろう。 3 皆川満寿美はこのことを正しく指摘している。(羅川真理茂の『ニューヨーク・ニューヨーク』について。)(…)けれども、この作品はやはり、日本の「少女マンガ」を定義するとも言える『トーマの心臓』や『風と木の詩』以来の系譜に」連なっていると読める。描かれているのが女性同性愛ではない、というその一点において」(ウェブサイト「いろんな大学非常勤講師研究室」) 4 松浦理英子『親指Pの修行時代』には、ヒロインが最初の恋人正夫と「ホモごっこ」をして「男同士」であることの甘美さを味わうくだりがある。「正しい夫」のこのかすかな逸脱に主人公はときめくのだが、この細部はコンヴェンショナルな関係の中で起こるだけに、それ以後の一目を引く逸脱のスペクタクルにも増して感動的だ。 5 もちろんこれには種々の要素が絡んではいる。以下の激烈な二重の自己否定の告白を参照されたい。「物心ついて以来、私は、女である私自身が大嫌いでした。女だということは、弱くて情けないつまらない生き物であることでした。美しさや正しさは男のもので、女の価値はせいぜいその男に認められることだと思い、そういう存在でしかない自分がいやでならなかった。/「やおい」というのを御存じですか? 最近やっとそのメカニズムが女たち自身の手で解明されつつあります。乱暴に言い切りますと、要するに、女性が男性同士の性愛に心惹かれる、あるいは欲情することを指す言葉です。拒食症が現実の中での自己否定なら、「やおい」はファンタジーの中での自己否定です。/私は、これも物心ついて以来なのですが、恋愛や友情は男同士の間にしかない、と思い込んでいました。(…)ですから、女が登場するお話などはなかから受けつけませんでした。/私は女が嫌いだったというよりも、女はこうあるべき、という「女」の「あり方」、要するにジェンダーが認められなかったのです。男同士の性愛を想像しないと欲情しないのは、性愛の面での女のあり方、受動的であることを認められなかったからです。受動的で情けない女という存在を考えただけで、私は現実に引き戻され、性欲などどこかへ飛んでいってしまったのです。ここで、「だからジェンダーがおかしい」といえればリブなのですが、私はもはや自分が嫌いでありすぎました。(…)「拒食症」と「やおい」、現実でもファンタジーでも、私は私を抹殺し続けました。抹殺することで逃避したのでした。この嫌な現実から、女であるという現実から」(中野冬美「自己肯定という思想」『全共闘からリブへ』インパクション出版会 1996) ★参考文献★ ・Kaja Silverman,“Male subjectivity at the Margins”(Routledge,1992) ・谷川たまゑ「女性の男色嗜好について」他、『女性学年報』10,12,14,16号(オルタナティブ、1989,91,93,95) ・フロイト著作集(人文書院) ・デイヴィッド・M・ハルプリン『同性愛の百年間』(法政大学出版局 1995) ・溝口彰子「ホモフォビックなホモ、愛ゆえのレイプ、そしてクィアなレズビアン――最近のやおいテキストを分析する」〈短縮版〉『クィア・ジャパン』vol.2(勁草書房 2000)、〈全長版〉『YAOIの法則』(produced by 三人淑女 2001) ・レオ・ベルサーニ「直腸は墓場か」、『批評空間」II-8(大田出版 1995) ・ジェシカ・ベンジャミン『愛の拘束』(青土社 1995) ・大橋洋一「普遍てもなく差異でもなく」、『大航海』特集 オリエンタリズム再考(新書館 1996) ・アンドレア・ドウォーキン『ポルノグラフィ』(青土社1991) ・Judith Butler,“Gender Trouble”(Routledge,1990) ・スラヴォイ・ジジェク「否定的なもののもとへの滞留」『批評空間』II-8(太田出版 1995) ★プロフィール★ 鈴木薫(すずき・かおる)目下故障してるもの、パソコンと右下奥歯(結局抜かれちゃうのかなあ……)。もう二週間くらい前だったか、駅に付いたエレヴェーターに二人きりで乗り合わせたおばあさんに「ほんと暑いですねえ」と言われ、その直後ドアが閉まったので「こんなところに閉じ込められたら……」と返すと「ほんとに死んじゃいますねえ」と笑っていたが、今や家から一歩出しただけで殺人的な炎天に閉じ込められる。皆さんほんとに毎日普通に生きてますか? 私は駄目ですねえ。涼しくなる頃ブログ再開します。 ブログ「ロワジール館別館」 Web評論誌「コーラ」05号(2008.08.15) 「新・映画館の日々」第5回:“それはヴァギナではない”(鈴木 薫) Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2008 All Rights Reserved. |
| 表紙(目次)へ |