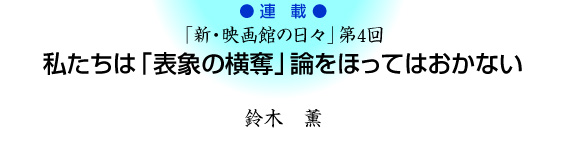|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
やおい/BLは、主にレズビアン/ゲイ・スタディーズの分野から批判的に評価されてきた。ゲイにファンタジーを押しつける、ゲイを「一角獣のような幻の存在」として描いており「不愉快」である、男性同性愛者の性を商品化した差別表現であるなどと批判されてきた。これらをまとめて表象の横奪(the appropriation of representation)の問題と呼んでおく。 (石田仁「ほっといてくださいという表明」 『ユリイカ』2008年12月臨時増刊号 総特集BLスタディーズ)> |
||||||||||||||||
|
1 それは〈私たち〉にとって何であるか 本稿の表題はエピグラフとして引いた石田論文への応答というよりは軽く Aさんからは、今年の一月にはじめてメールをもらった。TVアニメ『鋼鉄三国志』の設定を流用(appropriate)した私の小説『裏説[りせつ] 鋼鉄三国志』を通信販売で購入したいという内容だったが、鈴木の評論を楽しみに読んでいるという一行があったので返信で確認すると、最初に見つけたのが「アンジェンダレス・ワールドの愛の実験」(「カルチャー・レヴュー」31号掲載)で、その後、私のブログを知り、「カルチャー・レヴュー」や本誌「コーラ」での連載を欠かさず読んでくれているという。また、子供の頃出会った「三国志」の思い出について語り、私の評を読んで「久し振りに自分にとってのそうした感受性の原点を思い出した気がします」とあった。続くメールで、Aさんは、三国志との出会いについてもっと詳しく説明してくれた。評論を読んで関心を持った書き手(私)がたまたま三国志ものを書いていたというにとどまらず、彼女にとって三国志とは格別に思い入れのある対象なのだった。
「『何かを好きなこと』を自分で肯定するときに一番力になってくれるのは、ただそれが好きなことで幸福だったという、自分自身の記憶そのもの」だと思えるようになったのには鈴木の文章の影響が大きいとも書いてきていたAさんの言葉には、だから私の想像以上に深い意味がこめられていたのだった。メールのやりとりをしながら、知識量と文章から最初私は漠然とAさんを三十代くらいかと思っていた。それからもっと若いことに不意に気がつき、そうなると文面がまた別様に見えてきたが、それ以上勝手に想像することはやめて会ってみると、まだあどけなさの残るほどの若い人だった。 私の場合、批評的な文章は多かれ少なかれ〈怒り〉をきっかけにして書かれることが多い。「詩は怒りだ」という入澤康夫の断言を最初に見たときは当惑したものだ。入澤の詩と詩論をはじめて知った高校生の昔でさえ、すでに、書くとは、何を書くかを明確に意識した主体が、それをできるだけ巧みに「言葉によって表現」する、つまり内部にあるものと表現されたものとの距離をゼロに近づけるのではなく、《語に主導権を渡す》ことであるのだと私は経験的に知っていた。はじまりにおいて内部にあったものは何ものでもなく、ただ言葉の効果がすべてなのだ。だから、「詩は表現ではない」、つまり、先に作者の内面があってレモンを絞る(express)ようにそれを外へ押し出す “expression”ではないという入澤の教えは抵抗もなく入ってきてそこにとどまった(内面を伝えたいという当時の私の思いがいかに切実なものであったとしても)。しかし、感動が、琴線に触れたものが、「幸福の記憶」が書くことには先立つと、そしてそれは端的に「良いもの」だとはなおも信じていたようだ。 しかし、詩は〈怒り〉なのだった。不愉快で、良し悪しでいえば間違いなく悪に属する、どす黒い負のしるし。それが最初腑に落ちなかったのは、まだ、世界との軋轢にそこまで直接さらされなくてすむほどには私が保護されていたということなのだろうが、ひとたびそれが実感できたときから、ものを書くにあたってその認識はもはや私を去らなかったように思う。しかし、Aさんの手紙は、私の心なしの言葉を自分の思いで充填してくれる読者が実在することを、「己を知る」者のためにこそ最初は書いたし、実は今もそうであることを、自分が他者の共感を必要とする“死んでいない” 作者であることをあらためて思い出させてくれた。私の読者などさして無いにしても、そういうことは現実に起こっているのだし、起こりうるあかしとして顔のある読者がある日私の前にあらわれた。三島由紀夫は自宅の敷地内に入り込んできた男、本当のことを言ってくれと彼に迫って警察に引き渡された若い男を、(いつか自分もそこへ帰って行くべき)「荒野から来た」と表現したが、私の読者は私の過去の柔らかい部分から来たようだった。その日私たちは九時間話した。
インターネットのへヴィ・ユーザーであるらしいAさんは、そこでのやおいをめぐる言説の中で、「腐女子」がどのように表象され、どのように非難されているかに通じており、それに危惧を抱いていた。「腐女子」というカテゴリーを作った結果(作ったのは当事者でも、それが「横奪」(!)された結果)、いかなる権力作用がそれをめぐって働いているか。
私と直接やりとりをするようになる以前にも、反動的な言説に対抗するのにAさんは私の書いているものを参照したという(そのように役立ててもらえれば書き手としてこれにまさる喜びはない)。私もAさんの言葉をずっと参照しつづけた結果、本稿には、Aさんとの会話で得たことや、さらには彼女のメールからの具体的な引用を、本人の了解の上で入れさせてもらうことにした。 2 「やおい的感受性」
やおいは自分の母語であり、自分はやおいのネイティヴなのだとAさんは私に語った。これは個人的に非常によくわかる話だ。私の場合で言えば、男女の恋愛やセックスについて知識を得るよりはるかに早く、それははじまった(註1)。むろん、男女に対応する男男の関係についての知識ともそれは関係なかったし、男同士の関係性が根本にあるというものでも必ずしもない。男同士の表象とは、むしろ、それをより効果的に体現するものとして遅れてやってきた。唯一はずせないのは、それがエロティックであり、快をもたらすものであることだ。(だから、やおいを語りながら、「女性の性は怖れからはじまる」と繰り返す藤本由香里のような人には、少なくともこの部分には私はシンパシーを抱けない。)やおいというジャンルはまだなかったから、私自身はまさしく母語を覚えるように手持ちの断片でブリコラージュすることからはじめて、JUNEより先にGenetを読み(だから攻め/受けがやおいの発明品でないことを知っている)、英語の「ゲイ・エロティック・ライティング」(註2)まで(むろんこれは後年の話)行った。BLが本屋の棚にあふれていてそれを思春期以降に手に取った世代とは違うのだ。いや、Aさんを得たので、私は世代という言葉を使う必要がなくなったと感じている。
「歴史物」のもともとの作者はむろん男である。「やおい的感受性」(とAさんは呼ぶ)は、「感受性」であるのだから本来性別にかかわらず持ちうるものであるはずなのに、それが「腐女子」というカテゴリーに囲い込まれた結果、限定された特殊な人間にのみ属するものとされ、しかもそのこと自体女として「正しくない」と決めつけられる、そのような人間としてレッテル貼りがなされる恐しさをAさんは語った。 すでにお気づきであろうが、Aさんのこのロジックには、同性愛者というカテゴリーの成立についてのフーコーの考察に似たところがある。誰にでも(というときそれは当然のことのように男なのだが)潜在的に開かれていたものが、「種族」の属性とされることで、「異性愛者」と明確に区別される「同性愛者」が誕生した(いや、フーコーによれば、「同性愛者」というカテゴリーが作られたために「異性愛者」もできたのだが)。三国志の英雄は仮に男色を行なったとしても「同性愛者」や「ゲイ」ではありえないが、「やおい的感受性」もそのようにアイデンティティとしてではなくゆるやかに人に属する。それはセクシュアリティの一部、性的指向とはまた別の、しかし当事者にとっては重要な一部なのだ。むろん、空想のシナリオに登場するのが男であること自体、この世界にあって人が性別をどう感じ取るか、男がどのように表象されているかということにかかわるものだ。Aさんから教わった本であるが、『貝と羊の中国人』(加藤徹)には次のような記述がある。
オトコにはいろいろあるが、女には、「男」に対する「女」の一種類しかいない(紅一点論!)。というより、最初から表舞台には登場しない。出るときは“彩り”(男たちがホモセクシュアルでなくホモソーシャルに見えるように?!)だ。けれども、〈私〉たちはそうした女であることを忌避してやおい的なものに逃げ込んだわけではない。Aさんは自らのやおい的感受性を(で)発見するのに女を嫌う必要などなかった。とはいえ、成長してみれば、このヘテロセクシストな社会では、確かに〈私たち〉は、男との関係によってしか存在を許されない〈女〉に分類されているのだった。 だから問題は(ゲイの表象に特化しない)「オトコ」の表象と、その仲間に入れない(劣位の)〈私〉との関係だと〈私たち〉は考える。ところが、驚いたことには、〈女〉であることのみじめさに苦しむ哀れな女(註3)が、さらに劣位にあるゲイ(註4)のイメージを消費している、男が自分より劣るとされる女の表象を消費するように、女は下位にいるゲイの男を……などと、どうしたらそんなことが思いつけるのかわからない説明をする人がいるのだった。百姓がエタ非人を蔑むみたいなこの言い方は、これもAさん経由で知ったのだが、やおいにパラノイア的憎悪を抱いているらしいゲイ男性のコメントに対し、ある男性ブロガーがしていたものだ。私もこのブログは知っており、むしろ好感を持っていたので、Aさんの言う“リベラル系の男性ブロガー”が彼であると知ったときは信じられない思いだったし、過去のコメント欄にそういうやりとりを見つけたときは(Aさんは二度と見たくないと言っていたので、私は自分で探し出した)それ以上にショックだった。同性愛は生まれつきだから許してほしいとマジョリティのお情けにすがるに等しい論理で承認を求めるゲイ(男性)がいるように、彼は女の代弁をして、女はそうせざるを得ない状況に置かれているのだから許してほしいと言わんばかりに、そのゲイ男性と「腐女子」の間を取り持っていた……。
「ほっといてくださいという表明」(「ユリイカ」2008年12月臨時増刊号 総特集BLスタディーズ)で、「腐女子の「ホモ」は「[リアル]ホモ(ゲイ)」をつねに・すでに参照している」と石田仁は言うのだが、ジャンルBLの、少なくとも現代の日本を舞台にした作品に限定すればそう言えようし、その限りで石田の異議申し立てが有効であるのも、「腐女子」当事者を自認する女性研究者の言説に対して、彼が最近の「ユリイカ」の二度の増刊号(一度目は「総特集 腐女子マンガ大全」)にあれらの論考を書かねばならなかった理由も意義もわかるつもりだが、いかんせん、過去を振り返るのに「ゲイブーム」と言われた時代程度ではどうにもスパンが短過ぎる(註5)。 Aさんと会ったとき、私は買って間のない「ユリイカ」のBL特集を持っていたが、すでに引用したとおり、そういうものにはなるべく近づかないようにしているというAさんに「つねに・すでに」のくだりを紹介すると、彼女は一言、「身の程知らず」と呟いた。 石田の論考が対象にしたり、向けられたりしている相手では、だから本当は〈私たち〉はないのだろう。〈私たち〉は、改悛言説を吐き、ゲイ男性に申し訳ないと感じる、政治的に正しくあろうとしているような女たちではない。また、そうした人々も含む、彼女たちに介入しようとしつつそれについてのアンビヴァレントな認識が石田によって語られているような、BLの読者/評者/作者でもない。だからと言って、Aさんも言うとおり、「腐女子」と呼ばれることから〈私たち〉が逃れられるわけではない――〈私たち〉は、つねに、すでに、参照されている――のだから、これは端的にフェアでない。 ハンパに啓蒙され、表象すること自体が暴力だとか言い出す連中はとりあえず「ほうって」おこう。ここではただ、好きなものにあくまで執しつつ、一方で湧き上がる怒りを鎮めるために、少しばかり問題を整理して見通しをよくすべくつとめることにしたい。
3 Who’s afraid of the big bad male nude?
宮城県・黒石寺の“裸祭”蘇民祭のポスターがJR東日本に掲載拒否された一件はまだ記憶に新しいが、その理由は、JRの男性課長の言葉として最初に報じられたものによれば、胸毛などは「女性のお客様」が不快に感じるのでセクハラにあたるというものだった。事態を紛糾させた一因はこのセクハラという言葉にあったろうが――ポスターの写真を見、その記事を読んで最初に思ったのは、逞しい裸男が上を向いて口をO字形に開けたこの写真が、担当課長のホモフォビアを刺戟したのではないかということだった。これを見て女性が不快に感じるだろうか? もちろん、不快と思う人もいようが、「女性」なら不快に感じると決めつけられ、それを公然たる理由にされたことが私には不快と言えば不快だった。 このポスターを女に対する「セクハラ」だというのが腑に落ちないとして、では、どういうポスターだったら「セクハラ」と言いうるだろう? レイプを連想させるとして問題になった三楽のCM、と言ってももう知らない人も多かろうが、私はリアルタイムであれを見ている。しかも、TVにCMが流れるのを前夜自宅で見て、あくる日その続きを公共の場に貼られたポスターで見るという、なんとも“理想的”な受け手であった(本来男性主体が占めるべき場所として、CM制作者にも想定されていたかもしれないポジションであろう)。だから、抗議した女たちが過剰に反応したとか考え過ぎだとかいう話では全くなかったということの証人としても書いておく……男まさりの西部の女が荒くれ男たちに囲まれるCMを夜のTVで見た翌日、同僚と歩いていた地下鉄の通路で、前夜の女が泥まみれになりながら仰向いてこちらを見ている姿がアップになったポスターが目に入ってきたのだ。あっと思った。これがTVでは放送されなかったフィルムの続き……。そのとき同僚が、「何、これ、嫌な感じ」と呟いた。「どうしてこんなの貼るの?」 ポスターだけでも、彼女にもわかっのだ。嫌な感じ……「女性のお客様」が明らかに“不快”に思ったそれに、営団地下鉄の担当者は何も感じなかったとみえる(ついでに言えば、当時女性の職員は皆無だったはず)。「セクハラ」という言葉はまだなかったから、同僚も私もそう名づけることはできなかったが。 三楽のポスター(たとえば)がなぜ女にとって「不快」で「セクハラ」かといえば、自分もまた同じように男たちの性的なまなざしの対象にされる――被害者の西部の女(乗りこなされたじゃじゃ馬)に注がれたのと同じ目が、今度は自分に注がれる――公共空間が、それに対してはポスターの女の無力なまなざしで対抗するしかすべのない、ヘテロ男の性的ファンタジーで充満した出口のない空間に変わる――いや、私たちが生きる空間がもともとそのような逃げ場のない、地の果てまで(男の)へテロセクシュアリティで舗装された世界であることを見せつけられる経験であるからだ。 黒石寺の女性住職は、都会の娘に何がわかる、てなことを言ったらしいが、都会の娘は何も言っていない。JRの男課長が言ったのだ(註6)。マスメディアの報道のみを根拠にした臆測をあえてするが、男が性的なまなざし、しかも男のそれの対象になる可能性を、彼はあのポスターに見て不快になったのではあるまいか(それがもし快であったとすればますます不快に)。そう感じたのは自分なのに、「女のお客さま」が不快なことにした(あるいは、「女」にされて彼が感じた不快感か)。裸男が現実に迫ってくるならともかく、男の表象を女は(男のようには)恐れたりしない。恥しそうなふりはしてみせるかもしれないが、それよりも面白がるだろう、あのポスターなら。 ニュースへの反響(もっぱらウェブ上の)で注目したことの一つは、JR東日本の決定を「差別」と呼ぶ者の多さだった。いわく、胸毛のある人への差別だ、いわく、女が好むきれいな男なら何も言われなかったろう。「差別」という言葉は今日ではいくらか護符のようなものになっているのかもしれない。やおいはゲイ差別というのも言う方は切札のつもりだろうし、それだけで反応してしまうリベラルな(と自らを思う)男性ブロガーもいるくらいだから。あるいは、美人コンテスト反対の論理を無意識になぞったのかもしれない。女の好みばかりが優先されると文句を言う男もいたが、これは、女は差別されていない、今やむしろ優遇されているじゃないかといったうわ言をいう層と重なっていよう。JRは女に媚びてる、女の裸ならよくて男の裸はだめだというのは差別だなんで奴まで出てきて(これはゲイ男性のサイト)、ゲイでもストレートでも男のバカさ加減は同じと思わずにはいられなかった。 私がこの事件に注目したのは、ホモセクシュアル/ホモエロティック(あのポスターの絵柄をそう読んでもいいだろう)な表象に出会ってホモセクシュアル・パニックが掻き立てられたとき、「女のせいにする」というのが、「腐女子」バッシングの図式とよく似ていたからだ。蘇民祭のポスターは「女性向け」というよりは「男性向け」だったが(といっても、むろん、写真の男は好みでないというゲイ男性も、胸毛の好きなストレート女性もいよう)、そのことは抑圧されて、「女性に対するセクハラ」という、曖昧な、しかし、「ゲイ差別」にも似た俗耳に入りやすい言葉に置きかえられた。このすりかえは、「女性向け」とされるイメージでホモセクシュアル・パニックを起こした男が、もっぱら「腐女子」のせいにするのと構造としては同一だ。 「ホモエロティックなもの」がもっぱら「腐女子」に帰せられるとき、人はゲイ男性の存在を安んじて忘れることができる。「ホモエロティックなもの」の表現(担い手の性別は問わない)が抑圧されることこそゲイ差別であろうに、いまや「腐女子の特殊な好み」(と見なされたもの)を公の場で語ることを抑圧する発言が平然となされている。ほっといてくださいとは、第一に、そうした風潮に対する当然のリアクションではないか?
4 黒鳥と一角獣 冒頭にエピグラフとして引いた石田の文章に登場する一角獣が、はじめて目を通したときから気にかかっていた(引用では省略したが、やおいがゲイを「一角獣のような幻の存在」として描くと発言しているのがキース・ヴィンセントであることは割註で示されている)。後註によれば96年の「ユリイカ」での小谷真理との対談からの引用で、今、本が見つからなくて文脈は確かめられないのだが、仮に孤立した比喩として「一角獣」というものが選ばれたのだとしたらそれはいかにも非日本的だ。つまり、そのエキゾチシズムにおいて。だが、少女マンガを考慮に入れれば、むしろ日本人読者にとってそれはすでに親しいイメージであるから、そうした事情をよく知っているヴィンセントが日本人のためにこの例を選んだとも考えられる(だが、そもそも日本人であればこれは例として選ばないと思われるので、一角獣が西洋の文物であってさえ、ここにはオリエンタリズムの匂いがする)。 もしこれが、アメリカ人であるヴィンセントが彼のように日本の事情に詳しいというわけではないアメリカ人の聴衆に向かい、日本では女性を主たる書き手/読み手とする「やおい」というものがあり、そこではゲイが一角獣のような幻の存在として描かれています、とでも発言したのだとしたら、「一角獣」が日本で知られているか知られていないかはもとより一般アメリカ人の知識/関心のほかであろうから、私が上に書いたような問題は生じず、「一角獣」という比喩は「現実には存在しない生物」というデノテーションのみを聴き手に与えて、いかにも幻の存在らしくすみやかに消え去るだろう。 しかし、日本の雑誌に載った日本語による対談の中の「一角獣」は、それにまつわる少女マンガ的コノテーションゆえに、私のようなよそ見をする読者(肝心の「表象の横奪」問題へまっすぐ行かない)にかくのごとき道草を食わせることになった。そもそも「一角獣」というのは「不愉快」な代物だろうか? 石田論文では直前に章のエピグラフとして「化け物にされてしまう[ゲイの]友人」云々という溝口彰子からの引用が置かれているため、その取り合わせから、やおいはゲイを「化け物のような存在」として描いており「不愉快」だと読者は容易に読みかえることができようから、「一角獣」という語は単に黙って掌に置かれる「貨幣」として消費され意識に上ることさえないのかもしれない。しかし、道草を食いながらも見逃さない私のような読者には「一角獣」がひっかかるのだ。 不意に私は思い出した。「幻の存在」というべき自らの象徴として、ある動物(架空のではないが)を選んでいた日本人作家がいたことを。性的にも、政治的にも、ここは「流刑地」であり自分の居場所ではないという感覚を持ちつづけていた。自分を受け入れない「地上」への呪詛は、彼をロマン主義の末裔にし、「幻想小説」へと導いた。中井英夫。このマイナー・ポエットが自らの疎外感を託した動物とは黒鳥だった。三島由紀夫とほぼ同世代だった彼は、戦後日本に対する違和感を〈幻想小説〉と呼ぶ形式であらわした。だからファンタジーとしての一角獣も許されると言おうとするのではない。直接的な変革が不可能と思われるとき、人は望みを地上でないところに向ける。「ファンタジー」とはつねに社会的なものである。自律=孤立したファンタジーなどありえない。 その意味でも、ここは自分の故郷ではないという意識を終世持ちつづけたロマンチスト中井の作品が、実は人並みに(ここでは人=男のこと)ミソジナスであったことは注目に値する。言うまでもなく、伝統的な文学的意匠においても、女であるとは地上に縛りつけられることと同義だった。そして、男が(そして男同士の関係が)理想的な高みへの飛翔を目指すその分、取り残される女たちは対照的に、粗野で、惨めで、「現実的」でなければならなかった。その意味で彼にもまた逆説的に地上と縁を切ることは不可能で、彼の憎む地上の象徴としての女たちの表象を「横奪」しなければならなかったのだ。これは、男同士の仲を引き裂くものがつねに邪悪な女である小説を書いた(中井が短歌雑誌の編集者として見出した)歌人の塚本邦雄の仕事とも軌を一にする。 それでも(それゆえに)中井には多くの女性読者がついた(彼女らには中井以上に地上に居場所がないかもしれないことは、彼には思いもよらないものだったとしても)。その一人から、萩尾望都の『トーマの心臓』を、読んで下さいと渡されたという話を中井は書き残している。『トーマの心臓』を読んで中井は当惑したという。どうして自分にそれが贈られたかわからなかったのだ。〈私たち〉にはわかるし、彼がそれを受け入れることのできなかった理由もわかる。彼の女性読者こそ、通常の男流作家とは異なる彼の世界にオルタナティヴを、こことは別の場所への入口を見出していたのだろう。たとえそこが原理的に「女」には拒まれている場所だったとしても。自分の作品がそうした感受性と通底することを彼が認めえなかったのは残念なことだ。作品の上では制度的ミソジ二ストであった彼の作品が女性たちに「誤配」された結果、反動的なものでなくなる可能性に彼は気づけなかった。あるいはそれは彼の作品が未来にまで生き延びる唯一のチャンスかもしれないのに。 これは石田の言うやおい/BLの「自律」とも関わる話だが、谷川たまゑの「女性の美少年嗜好」論は、やおいに関して、このようなロマンチックな「地上」からの切断(彼女の場合はそれは心理学的装いの形を取った)――それはとりもなおさず、社会的文化的な影響及び影響を与えることからの切断である――によってファンタジーとしての「やおい」(彼女はそうは呼ばないのだが)を「自律」させ、現実の男性同性愛とは無縁なものとしようという試みの草分け的なものだ[彼女の議論は水間碧名義で一巻にまとめられており、それについてはブログで触れたことがある。http://kaorusz.exblog.jp/4212121/]。もう何年前になるか、ほかならぬキース・ヴィンセントがやおいについての講演を行なったとき、彼の手元に置かれていたのは谷川が「女性学年報」に載せた論考のコピーの束だった……参考資料が最悪、と思わずにはいられなかった。 中井英夫のケースから思い出した話が二つある。一つは、佐藤亜紀がマリオ・プラーツから引いている例なのだが、十九世紀末にボッティチェルリの真作として通用した作品が今日では素人目にも違いがわかるという話だ。贋作者が見ていたボッティチェルリは「同時代の大多数の鑑賞者」の目に映っていたボッティチェルリで、贋作者はそれを忠実に再現した。だが、時が過ぎると、絵はそのままなのに見る方の目が変わってしまい、それがボッティチェルリに見えたことが不思議に思えるくらいなのだという。「それでもボッティチェルリの真作は快楽の装置として機能し続ける」(註7)。中井の場合、彼もまた「同時代の大多数の」(註8)彼の読者のようにしか彼自身の作品を見られなかったため、これはあなたの作品に似ていると『トーマの心臓』を差し出されても、唖然とするしかなかったのだろう。 私が連想したもう一つの例は、これも絵画だが、アンリ・ルソーと同時代に官展(サロン)で名声を博していた画家たちの作品のその後の運命である。周知のとおり、正規の美術教育を受けなかったルソーは、アンデパンダン展によって絵を発表する機会をはじめて得た。では、ルソーを拒否したサロンの、入賞者である画家たちの絵はどんなもので、その後どうなったのだろう? 彼らの名前は忘れられ、今日その絵を見ることすら難しいらしい。なぜなら、「多額の費用を使って国家が買い上げた彼らの絵の多くは、美術館の倉庫の奥深くに積み重ねられたままになっているからである」(註9)。しかしルソーは、同時代の凡庸なアカデミシャンの作品を素晴しいと本気で思い、忠実に模倣すらしつつ、結果としてはあのような絵を描き上げた。 生前そこそこの評価を得た、恐らくは現在でも熱心な少数の(少数であることを誇りとする)愛読者を持つであろう中井は、ある小説で主人公を、実用に堪えぬ埒もない幻想陶器と言われる作品を制作する陶芸作家に設定していたが、結局のところああした陶器は、その死後、倉庫に押し込められてしまったのではないかという気がしないでもない。すでにその贋作(エピゴーネンと言ってもいい)は本物とは見えなくなっているのかもしれない。ルソーのように目は別のものを見ていたとしても、時の経過による視覚の変容を越えて「快楽の装置として機能し続ける」だけの「強靭」な作品を彼が書きえていたかどうか。それは結局のところ、どれだけそれが「横奪」に、異なる読みに堪えうるかにかかっていると思う。中井は彼の未来の読者の訪問に気づけなかった。それが仮の分類である「幻想小説」の枠を離れて『トーマの心臓』と並べて置かれるとき、別様に見えてくるであろうことを知らぬままだった。未来の読者の目には――いや、未来を待つまでもなく、〈女〉という異人の目には――彼の作品がそう見えるということを理解せず、理解しようともしなかった。 ストレートであれゲイであれ、男が認めたくないのは、女もまた男であるということだ。自らのうちなる女性性を認めることができる男性も、逆に現実の女もまた自分と同じとはなかなか認めえない。中井もまた、女の側からの――“身の程知らず”の――アプローチを受け入れ、少女マンガに自らの分身を見出すことはついにできなかったのだ。
5 表象の流用
「もちろん異性愛男性こそが女性イメージを圧倒的に性的な存在としてパタン化し領有してきたことは論を待たない。そのため「女の側だって少しくらい好き勝手してもいいのでは」という声もある。ただしもちろん、そういった考えは溜飲を下げる以上の効果はもたらさず、生産的な批判ではない、と考えられている」(石田、前出) 石田はこのように述べるが、男性による女性イメージの「領有」は、なにも“異性愛男性”に限った話ではない。何年か前、タレントのピーコが、深夜番組で「爆笑問題」相手に、「[ピーコは]女らしい」「ピーコさんてほんとに女なんだね」といいった反応を引き出すような自己規定を繰り返し、好きな男の顔を見ているだけでいい、何もしなくてもいい、と自らがrepresentする女性主体の脱性化(これは異性愛男性による性的対象としての女の“パタン化”と矛盾しない)をはかりつつ、ホモフォビックなヘテロセクシズムの強化(問題なのはピーコが生物学的に女ではないことであるかのように言われ、ピーコの男への愛は女が男に対する愛と同じものとされる。すなわち、“真の”男から男へ向ける欲望は存在しないことになる)を行なっているのを目撃したことがある。ゲイ男性が女性性をも兼ねそなえた存在としてふるまうことで、かえって生物学的女性の本質化が促される効果を生むのはよくあることだ。(これはピーコではないが)はなはだしい場合は生物学的女性に向かって女の道を説きはじめるし、それをもてはやす女もいる(註10)。 かくも完璧な女性性の横取りと押しつけが横行する中で、「女の側だって少しくらい好き勝手」とか、「溜飲を下げる」というのは、あまりリアリティのある言葉とは思えない。そんなことではどうにもならないほど男の側からの領有は凄まじいのだが。そして、ピーコがこれだけやっても何も言われないのは、言うまでもなく男だからだ。だから少しぐらい、と私は言いたいのではない。この非対称を前にして言葉を失うのではなく、次のように饒舌になることが信じられないと思うのだ。 「いったん「他者」として切り分けた存在を、「私」との関係で非対称に配当し、お決まりのパタンでくり返しイメージした後に葬送する。この表象の横奪の問題は、現代(ポスト植民地時代)の諸研究で、すでに重要な論点として認識されている。たとえばハワイ、スペイン、沖縄が、経済的宗主国によってリゾート地として創出-消費(開発)」されてきた経緯があり、しかもこの「開発」は現地のイメージを一方的に創出-蕩尽する営みと密接不可分だった。とすれば、「女ではない他者」のイメージをパタン化し領有するやおい/BLも、微睡みの中にいることは許されない」(石田、前出) 女にとって男は「他者」だろうか。とんでもない。男にとって「他者」とされてきた女は、それ以外に自らのイメージを持たず、そこから抜け出すときには「男」となるしかない。なぜなら、女ではないものこそ「男」とされてきた(それゆえ男はなんとしても自らが「女」の位置におとしめられることを拒む)からだ。「男」との関係で非対称に配当され、お決まりのパタンでくり返しイメージされた「女」とは空虚な存在であり、一方、「男」の側にはすべてがある(ように見える)。権利がないのに占有した他者の領域で、女がなりたいのは「女ではない他者」ではなく、「女ではない主体」だ。(エロティシズムの観点から言うなら、そうした主体こそが、主体が崩壊するときの、すなわち「受け」としての十全な享楽を持ちうるように思われる(幻想される)。男によって“パタン化”され領有されてきた女には、まず、この意味での主体がない。したがって彼女にとっての「他者」もありえない。 上記の引用で、石田は、女が「他者」を植民地化しているありさまとしてやおい/BLを描いている。「リゾート地として」「現地のイメージを一方的に創出-蕩尽する営み」であると。しかしこれは、あまりにも男女の権力関係を無視した、男→女を、単純に女→男へ反転させただけの安易なやり方ではないか。私は以前、ある発表(残念ながらやおいについてではなかった)で使うためにappropriationという概念(石田が表象の横奪と言うときの「横奪」)について、文化人類学が専門のMさんに教えを乞うたことがあるが、それによればappropriationとは、たとえば宗主国から《「押しつけられた文化イメージを現地で逆手にとって観光資本にするとか、「グロテスクな大文字の他者としての我々」イメージをとっかかりにした》文学作品を書くとかいう意味でも使われるということだった。すでにある資源を加工して、好きなナラティヴに再構成する――やおいもこの文脈で語れると思うという彼の言葉に力を得て、私はやおいに関して、好んで「流用」という訳語を使ってきた。 文化資本を持たない女は、男の表象を流用して(それは男から見れば簒奪であり、権利のない占有/領有だ。“女の分際で”“身の程知らずに”そんなことをしているのだから)やおいを書く。だが、それは男を植民地化しているのではない(そんな力があるわけがない)。男についての表象資源はけっして当事者だけのものではなく、《あらゆる立場からのあらゆる目的での流用に「開かれている」》(Mさん)はずなのだ。それが具体的な場でどう働き、どのような意味を産み出すかは注意深く見ていかなくてはならないだろうが。 ポストコロニアル的やおい理論(?)の見取図としてはこのようなものを勝手に考えていたので、正直、石田のような適用のしかたにはびっくりしてしまった。 男女間の権力関係は厳然として存在する。少女マンガによる「西洋」の“横奪”が西洋の側からの異議申し立てを受けたためしがないように、「女」による男の表象もまた本気で受け取られはしない。後者は前者を歯牙にもかけないから……。やおいにおいて表現された(正しくない)同性愛者のイメージしか持ち合わせなかったので「青年の家」の宿泊を拒否しましたと証言した自治体があったろうか? 男には女が表現できる(女自身によるよりも巧みに)と信じられる一方、女には真の男が表現できないとされてきた(女形と宝塚の男役の非対称を見よ)。光源氏の遍歴は感情の放蕩だからあれは男ではないと中村真一郎は言っている。要するに、紫式部は女だから男が書けなかったというわけだ(男は性に関してもっと即物的だというのだが、この「即物的」という言葉、周知のとおり、男はロマンチストだが女は、といった文脈では女に帰せられる。要するに、男でないもの・男を補完するもの=女という形態に納まりさえすれば、男にとって論理的一貫性などどうでもいいのだ)。 やおい/BLに対する批判も、この、「女の描く男は男ではない」というなじみ深い主張の一ヴァージョンに過ぎないというところが確かにある。そうなるとこれはゲイ表象というより、むしろ女性による男性の表象一般にかかわってくる。それがゲイ表象に特化されたことは偶然とは言えまいが。 それにしてもやおい/BLは本当にゲイの「具体的」差別につながるのだろうか? 男の表象は誰のものか? やおいが男の表象を使って男同士の関係性を描くとき、それは「男」の表象であるという一点で、ストレートの男をも脅かす(それが「ゲイの表象」ではなく「男の表象」であるために)。ゲイでない男がそうした表象によって、わが身に男のエロティックな視線が向けられる可能性を知れば不安も覚える。 だが、それが女の手になるものであれば、すなわちその表現が贋物と認定されれば、「男の友情」であるものにそれが理解できない「女」が、勝手にエロティックなものを「仮託」して誤読したと決めつけてしまえば、そして、世界の中で男にとっての「他者」、男に対する「女」というポジションしか取りえない女が、分をわきまえずに妄想した、彼女の本性に反する「間違った」セクシュアリティであるとされれば、ストレートの男は安心していられる。 そもそもappropriationという言葉を私が知ったのは、デイヴィッド・ハルプリンの『同性愛の百年間』で「専有」などと訳されていた語(の原語)としてだった。Mさんからは、抵抗的なappropriation(カルチュラル・スタディーズや文化人類学)と収奪的なappropriation(フェミニズムやセクシュアリティ研究)はそれぞれ独自の理論から出てきた批評概念だと教わったが、これをあてはめるなら、『同性愛の百年間』に収められた「ディオティマはなぜ女性なのか」という、プラトンにおける女性性の「横奪」を語って間然するところのない論文の場合は後者、オリエンタリズム的イメージの押しつけを逆手に取って観光資源にしてしまうのは前者になる。やおいも、劣位に置かれた女性がすでにある表象を使って自分たちのためにエロティックな表現をしているのだから前者と言えよう。 そうなると、石田のようにゲイ表象の女性による「横奪」(これはむろん収奪的)を言うのは、女性とゲイによる、表象資源の奪い合いということになるが、しかし、女性表象を「横奪」する男は、すでに述べたように女を女自身よりもよく知っていると称しうるのに、腐女子は(“良い”腐女子は)、石田が表象の横奪だと言えば即座に謝ったり自己点検につとめたりするのでこれは非対称だ。同じことでも、女がする場合と男がする場合では効果が違う。男による女の表象を女は内面化して自らをまなざすが、やおいの場合その逆がありえないのはゲイ男性が一番よく知っていよう(註11)。 “身分制度”が強固であり、“御主人様”と“婢”の距離が無限大である社会では「やおい」は成立しなかったろう。それより前に、ジェンダーを横断した同一化がありえなかったろう。しかし、“御主人様”の方は男の特権でそれができた。御主人が婢にかりそめに身を落し、女性性をも体現できることは、男が優れていることのあかしだった。だからこそソクラテスは巫女ディオティマに教えを乞うという形で、男の優越性をそこなうことなく愛についての知識を完全なものにしえたし(しかもその愛とは、最初から最後まで――妊娠や出産の譬喩を頻出させながら!――男同士の愛である)、時代は下ってフローベールは「ボヴァリー夫人は私だ」と言いえたのだ。稀代のミソジ二スト、ボードレールが、「ボヴァリー夫人は男だ」(女にはボヴァリー夫人のような想像力はありえないから、と女を蔑みつつ)と応じて彼の仕事が「横奪」であることを明らかにするとき、かえってそれはフローベールの栄光となりえたのだった(註12)。
6 “男はゲイ小説書きませんものね”
『赤壁の宴』は、三国志の登場人物である呉の孫策と周瑜の関係を濃密に描いた女の作家の小説である。著者自身は男の友情を書こうとしたらこうなったと述べており、私の趣味から言えば文章が通俗に流れるところが残念だが、しかし、二人の関係は非常によく描かれている。この小説の二人は親友(実際、その交わりは「断金の契」という言葉を歴史に残す)というより主従の方にウェイトがかかっていて、周瑜は孫策を気軽に伯符と字で呼んだりはしないが(って、そういう“策瑜”のイメージどこから来たんだw)、非常な美男子であることは(これも史実である)変わらず、孫策はお前が女なら抱いてやったのに、てなことを言いもする。だが、周瑜の抑圧が非常に強く、孫策は周瑜さえオーケーならと実は思っているふぜいだが彼がついに本心を見せないのでついに結ばれぬまま……と言うだけですでに読みたいとお思いになった方もいようが、こういうのが我慢ならない人もいるのだとAmazonのレヴューを覗いて知った。 確かに、こんなうじうじした周瑜なんてイヤ(これは周瑜じゃない!)、という向きもあろうし、それはわかる気がするが(私はこれはこれでスキ v)、やや変わった理由からこの本を激しく非難している女性がいて、それが傑作だったので紹介しておこう。帯には「女性でなければ書けなかった」とあるのだが、件のレヴューアーいわく、 女性でなければ書けなかったなんて、同性として恥ずかしい、 そりゃ、男はゲイ小説書きませんものね! なるほど、これがゲイ・イメージの横奪というものか! 小説がではない。このレヴューがである。 彼女は小説に横溢するホモエロティックなものが、男同士の友情と男同士の性愛の境をかき乱していることを知っている。内容的にもそれを越えるか越えないかが問題にされているわけだが、周瑜は越えられなかった(しかし、孫策の死後、抱かれてしまえばよかった、それなら今頃こんなに思い出さずにすんだろうと悶々とするのだ。いいでしょう?)。しかし、そこまで行けば越えたって越えなくたって同じである! そのとき、この一種のホモセクシュアル・パニックに襲われた女性は何をしたか。この小説を「やおい」に分類したのだ。私個人としては全然オーケーだけど、彼女の文脈では、それは作品の信用を落す行為である(その意味で「やおい」とは差別語だと言える)。著者が男性であれば、彼女とてそういうことはできなかったろう。いや、そもそも彼女の信ずるところでは、男性であればそんなものは書けなかったはずなのだ(「女性でなければ書けなかった」という帯の文句がそれを保証すると同時に彼女を憤慨させる)。彼女によれば男は「ゲイ小説」(同じものを女が書けば「やおい」である)を書かない――とは、つまり、ゲイ男性は存在しないということだ。 彼女は何を言っているのか。彼女にとって、〈女〉が(彼女が、そして彼女と“同性”の者たちが)第一に配慮すべき相手は(ヘテロセクシュアルの)男性なのだ。自らの性的ファンタジーを男もいる前で披瀝した“同性”のはしたなさに赤面し、そんな女ばかりじゃない、どうかあの女と同じだなんて思わないでくれと、「男の人」に懸命にアピールしているのだ。そういうのはゾーニングしてほしい、「女性向け」とラベルを貼ってほしい、歴史小説と銘打って表舞台に出てこないでほしい。(それにしても「同性として恥ずかしい」という言葉、本当はそれ自体「異性」にしか顔を向けていないのがまるわかりの、かなり恥しいものだと思うぞ。) 「表象の横奪」――“男はゲイ小説なんて書かない、書くのは腐女子だ”――の核心は、やおい/BLにおける「同性愛者」の表象が「正しい」か否かよりも(それは個々の作品の水準に帰せられよう)、むしろこの、ゲイ男性の存在の否定を水も洩らさぬものにする構造的な問題にあるのではないか。 「男の世界」(ホモソーシャル/ホモセクシュアルなものを含む)であるものに女が(“身の程知らず”に)アクセスすること自体が、本来、禁じられた/不適切な行為なのだった。それが「禁断の世界」であるのは、男性同性愛が禁じられているからでも、また、女が性的な表現にアクセスするのが禁忌だからでもなく(それとも関連はするが)、ジェンダー秩序にゆさぶりをかけるものでありうるからだ。それは男の領域を女が不法に占有(aprropriate)することだ。(“男性”同性愛も男の領域である。ミソジニスト/セクシスト/ホモフォウブだった吉行淳之介は、女に絶対なれないものが一つだけある、ホモだよとウーマン・リブを揶揄した。)その意味で、やおい的なものを論じながら、女性読者を制度的に想定したジャンルBLに事実上、話を限ることは、そうした表象に「女性向け」(“男はゲイ小説読みませんものね!”)とラベリングすること同様、その侵犯性を少しでもやわらげようとするしわざであろう。 7 ファンタジー、真理、フィクション――やおい化する欲望
切断しよう、「自律」しよう、「占有」ではないものとして肯定しようとする動きは(むろん幾分かは「ゲイにファンタジーを押しつける」と言われることへの反作用であろうが)、すでに挙げた、「女性の美少年嗜好」は現実の同性愛者と関係がないと言いつのる谷川たまゑ=水間碧だけでなく、「ユリイカ」の前回の特集での上野千鶴子にも(これは今回の特集で石田が指摘している)、今回の小谷真理の「C文学」をめぐるおしゃべりにも見られる特徴だ。 これに対して、それはもともと「男の」ファンタジーだったものを抵抗的に「流用」していると〈私たち〉は主張するものだ。 最後に、恐らくは「やおいネイティヴ」ではない主体による、制度的にジャンルBLが存在するわけでもない状況下での、「やおい的なもの」との出会いを語るエピソードに触れておきたい。 と大きく出たが……ほとんど実質はないに等しく、その文章が載っていた本自体見つからず(家のどこかにあることは確か)、本文は読んでいなくて、あとがきの一部に過ぎないのだが。要するにこういうことだ。ポルノ映画の歴史を研究した“Hard Core”というずいぶん前に買ったままの本があって、そういう本を持っていることすら忘れていたのだが、先日、appropriationという語についてのMさんとの交信記録をたどるうち、彼へのメールでこの本に言及しているのを見つけた。この本のあとがき(それだけ先に目を通したらしい)で著者は次のように書いている――私はこの本を書くために(当然ながら)多くのフィルムを見たが、その中で一番萌えた[意訳]ものは何であったか? それはmarried womanである私に向けたものでは全くなかろうと思われる男同士のイメージであった。 そのことの意味について彼女がそれ以上書いていたわけではなさそうだ(そうであればメールでさらに触れたろう)。これはぜひ本を探し出して彼女の研究を読まなければ。今はただ、この「誤配」をめぐって、少しばかり覚え書きを記すにとどめたい。 既婚の女のためのポルノグラフィが考えにくいのは、彼女の性的欲望が家庭内に封じ込まれ、もっぱら夫との関係のうちにあると考えられるからだろう。それは生殖という目的に添って組織されたセクシュアリティを持ち、思春期に月経がはじまって自分が女であることを自覚し、異性間性交し、妊娠し、出産し、子育てをして、更年期を迎える女だ。 だが、むろん、そんな女などどこにもいない。 彼女は現実の異性愛に飽きたらず、ゲイのイメージを利用したのだろうか? これは必要悪であり、いつの日か「[異性]愛の再発明」(ランボー)が実現した暁には、男との性愛における彼女のみじめさは取り除かれ、彼女はもはやゲイポルノに性的昂奮を覚えなくてすむようになるのだろうか? いや、異性愛が再発明されることがあるとすれば、それは異性愛が唯一の「正しい欲望」ではないと認められる時だろう(それに、再発明される日まで異性愛のすべてが〈悪〉というわけでもあるまい――そこまで異性愛を「ガチ」と思い込まずともいい)。 ゲイポルノで「萌え」られる彼女は、幸いなことに真理に――彼女の「正しい欲望」に――至りつくことがない。 彼女は女であることのみじめさから救われるためにゲイのイメージを利用したのだろうか? いや、むしろ、彼女はやおい化することによって、男のファンタジーを救うのだ。彼女の欲望はゲイのファンタジーを「やおい的なもの」にする。同じものに性的昂奮を覚えても、その主体が女であれば「やおい」である――だから、(やおいが差別するのではなく)「やおい」は差別語なのだ。だが、そのとき、ゲイのファンタジーもまた(ひいてはゲイ・アイデンティティそのものも)、それが仮の命名に過ぎず、自分が単一の実体ではなく複合的に構成されたフィクションであることを、「自律」したものではありえぬことを明かすだろう。享楽する者の身元をそのとき誰が尋ねようとするだろう? ★プロフィール★ 鈴木薫(すずき・かおる)突然インターネットの接続が切れました。ひかり電話もダウンしました。自サイトも過去のメールもなしに今回の原稿は書けないのでネカフェで書き上げました。実家からBフレッツの故障専門の番号にかけたら、1のボタンを押して下さいと録音の声に言われました。ダイヤル式なんですけど。ひかりにした方もダイヤル式。親の遺産の黒電話二台持って携帯持たない人です。/「今回のテーマについては最近のブログでも書いています(というか、やおい論専門ブログになりつつあるような)。併せてお読みいただくと面白いかもしれません。/なお、〈私たちは二人だった〉とはいえ、〈私たち〉とは〈私〉の複数形ではなく、あくまで〈私たち〉と名乗る者が他をも代表して語る非対称な形式です。私の文章が(当然ながら)Aさんの意見を完全に代弁しおおせているわけではないことを念のため付け加えます。 ブログ「ロワジール館別館」 Web評論誌「コーラ」04号(2008.04.15) 「新・映画館の日々」第4回:私たちは「表象の横奪」論をほってはおかない(鈴木薫) Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2008 All Rights Reserved. |
||||||||||||||||
| 表紙(目次)へ |