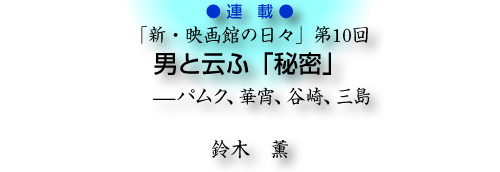|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
2006年にノーベル賞を得たトルコの作家オルハン・パムクの長篇小説『私の名は
実際には、これらの章は、語り手が一度きりで消えるか、繰り返し現われるかによって、二つに分けることができる。二回以上出てくる語り手は、“物語”――細密画師が殺された事件の犯人探しと、それに関連する一組の男女(カラとシェキュレ)の関係の進展――の進行役であり、彼ら自身が主要登場人物でもある(これが探偵小説だとすれば、この中に真犯人がいるわけだ)。
試みに、章の名を順に書き出し、複数回出てくるものはその回数をカッコ書きしてみる(逆に一度しか出てこないのは太字にした)。
わたしは屍
わたしの名はカラ(12)
わたしは犬
人殺しとよぶだろう、俺のことを(5)
わしはお前たちのエニシテだ(4)
ぼくはオルハン
あたしの名はエステル(5)
わたしはシェキュレ(8)
わたしは一本の木だ
人はわたしを“蝶”とよぶ(2)
人はわたしを“コウノトリ”とよぶ(2)
人はわたしを“Iリーヴ”とよぶ(2)
わたしは金貨
わたしの名は“死”
わたしの名は紅
わたしは馬
名人オスマンだ、わしは(2)
わたしは悪魔
わたしらは二人の修行者
わたしは女
これで語り手は20(「二人の修業者」は1と数えるとして)、「人殺しとよぶだろう、俺のことを」と言っているのは匿名の殺人者で、実は身許の明らかな語り手の一人とダブっているので1を引くと19にまで絞られた。ちなみに松岡正剛はこの小説について、「登場人物やら死体やら犬や木が語る」が、「このやり口は必ずしもめずらしいわけではなく、たとえば芥川龍之介の『薮の中』をはじめ、多くの作家がけっこう使う手だ。物語がミステリアスになるには、この手口がふさわしい。が、パムクはたんに語り手を変えただけではなく、すでに死んだ者や植物や動物にも語らせた。これがこの物語をなんとも異様にさせたのだった」(☆2)と、ずいぶん不正確な言いかたをしている。だいたい、『薮の中』のように、互いの言い分が矛盾して整理がつかないなどという稚拙な仕掛けはここにはない。「この奇妙で贅沢な引き延ばされたスリラーは、殺人者も含む計十二の視点から語られた五十九の章からなる」と書くジョン・アップダイクの方がまだしもだ(もっとも、後述するようにアップダイクも、他の点ではかなりいい加減なことを言っている)(☆3)。十二の視点とはまた急な減りようと思われるかもしれないが、「屍」と「オルハン」以外の一度しか出てこない語り手は、実は同一人物のペルソナだからこれで計算が合うのだ。
上の仕掛けは、カラ(形式上の主人公)がはじめて登場する第二章で、最後に彼がコーヒーハウスに入ってゆき、「咄し家」が壁に「犬の絵を掛けて、時々絵の犬を指さしながら犬の口調で語ってい」るのを見る直後に章が改まり、「わたしは犬」と犬の語りがはじまるのだから本来見誤りようがない。第一章では文字通り井戸に突き落されて発見されないままの屍体が語るわけで、この話全体がフィクションに他ならぬことのあざといまでの(かつ紋切型の)提示であり、「ぼくはオルハン」は一篇の結びで作者に擬されるシェキュレの息子オルハンの幼い姿での顔出しで(兄のシェヴケトには語り手としての出番はない)、(オルハン・)パムクの贋の署名だろう。
つまり、一度しか登場しない語り手(咄し家によって演じられたものも含め)の語りは作品の枠組に自己言及する部分であり、それ以外は、カラとシェキュレの恋物語および殺人事件の解決(これは彼らの結婚の成就の条件でもあり、カラは探偵役をつとめることになる)という、一篇の表面上のプロットにかかわるものだ。
実は最近まで、パムクという小説家についてはほとんど何も知らなかった。数年前、トルコの作家がノーベル賞を受けたことは知っていた。いや、トルコということさえ意識していなかったかもしれないが、村上春樹が賞を逸したという新聞記事に付随して出ていたのを目にした記憶はある。何やら政治的な状況に置かれた作家が受賞という小さな扱いではなかったか。村上春樹受賞なんて冗談みたいな話が本当にならなくてよかったと思っただけで、すっかり忘れていた。
それが、本誌10号に「特別寄稿」として載せてもらった論考(“父子愛”と囮としてのヘテロセクシュアル・プロット――トールキン作品の基盤をなすもの)の共著者である平野智子から『私の名は紅』について聞かされた。彼女が話してくれたのはもっぱら「咄し家」のことであった(ラヴ・ストーリーについては、通常そう読まれるようにそれがメインではないことが指摘された。私たちが前回トールキンについて論じたのと同様に、「囮としての“ヘテロセクシュアル・プロット”」の一種とも言える)。だから、「咄し家」についての以下の解釈も、平野に負うところが大きい――ほとんど受け売りであると先に断わっておかねばならない。
それにしても、小説の核心部分とも言える「咄し家」について、なぜ誰も何も言わないのだろう。といっても、そもそもパムクが日本において一般に評論の対象にされているのかどうかさえ、寡聞にして知らない。英語で読めるものをインターネットに探して、アップダイクのレヴューを見つけた。
はたしてアップダイクは「咄し家」についてかなりのスペースを割いていた。それまでの章で犬、木、“死”、紅という色、馬、悪魔、二人の修行者として語った「咄し家」は、最後に〈女〉として語る。アップダイクの文章を引こう。
なお、ここまでの『わたしの名は紅』からの引用は和久井路子訳に依ったが、上の「咄し家」の歌は重訳になるのをかえりみず、あえて英語から訳してみた。むろん、もとのトルコ語を知らないから訳の正しさを云々したいわけでは全くないが、この小説の核心をあらわすものだと考えられるフレーズの意味は英訳の方がよく出ていると思われたからだ。
この小説につきまとう二重性、とアップダイクは言う。しかし、「両性具有的な直観」を文字通りのものと考える私たちと違って、彼のいう両性具有性/二重性とは、次の引用に見るとおり、政治的な「東」と「西」のそれである。
アップダイクは、エルズルムの説教師によって、コーランの教えをないがしろにしたせいだと決めつけられている小説中のイスタンブールが抱える災いを数え上げているが、これは第二章で十二年ぶりに帰郷したカラが人から聞く話に直接拠っている。大火、疫病、戦争、贋金とアップダイクは順に並べながら、以下の部分については薬物のところしか拾っていない――「ならず者や反逆者がコーヒーハウスに集まって、夜が明けるまで教えに反する行いをしているのだと聞いた。いかがわしい貧乏人、麻薬中毒の狂人、非合法のカレンデリ派信者が、アラーの道に従っていると主張して、修行僧の家で音楽に合わせて踊ったり、自分を突き刺したり、あらゆるやり方で堕落したあげく、暴力的に犯しあったり、少年を見つければ相手かまわず犯したりしているのだと」(☆4)
つまり、コーヒーハウスというところ自体がいかがわしいわけで、人々が「預言者ムハンマドの道を外れ、コーランの教えを無視」することを憤る連中は、コーヒーと美少年の愛好をセットで目の敵にしているのだが、アップダイクの文章はそのあたりをネグレクトしている。同様のことは、ヨーロッパの町ではヴェールをつけない女たちが歩き回っているというすでに引用したくだりについても言えて、実はあの部分には、直前で次のような記述が先行していた。
この小説の特色と称して、松岡正剛は「欧米のメディアに訴えるところとなり、ノーベル賞をとる理由になった特色とおぼしいのだが、物語の全編を通して「東は東、西は西」という姿勢と哲学を徹底して貫いたことだった。パムクは、ここに全力を傾注したといってもいい」と言っている。もしそうなら、「東」ではそれが「甘美な習慣」となっており、登場する男たちはみな美少年が大好きであること――“主人公”のカラも、しかも結婚後にさえ、「かわいい男の子を追いかけた」「かわいい男の子や馬鹿騒ぎに熱中した」と二度も(妻となったシェキュレによって)言われている――を、「西」との差異として強調してもよさそうなものだが(アップダイクはともかく、松岡正剛なら)、触れてもいない。
実際には、少年への愛は、細密画師たちの芸術と切り離すことができないものであり、全篇を通して記述に入り込んでいる。また、「東は東」とパムクが主張しているというのも事実ではない。《この「東は東、西は西」という言葉は、終盤でエニシテを殺めた殺人犯(これは内緒)が「東も西もアラーの神のものだ」と言うと、カラが「東は東だ、西は西だ」とぽつりと呟く場面にも象徴的に使われている》と松岡は言うが、これは小説の登場人物の会話に過ぎず、カラの意見は即パムクの意見ではない(あたりまえだ)。実際、カラの科白は、もう一人の登場人物によって、「細密画師は傲慢でいけない。東だの西だの気にしないで、心に思うままに描くべきだ」と反論される。これに対して語り手は《「その言葉はまさに正しい」と俺はいとしい“蝶”に言った。「お前の頬に口づけしたい」》と応じるのであり、この場面もまた男同士の愛に浸透されているのである。
実は、「東も西もアラーのものなり」とは、コーランから引かれ、本書のエピグラフとして巻頭に置かれた三つの文句のうちの一つである。作中では、二人目の犠牲者となる“エニシテ”の死後の語り――「この自由を恐怖と歓喜をもって感じるや否や、わしはアラーの神が近くにおられることを理解した。同時に、絶対的な、何物にも比すことのできない紅い色の存在を敬虔な思いで感じた」――の中で、このフレーズは他ならぬアラーによって発せられる。壮麗な紅い色が近づいてくるのを感じて、“エニシテ”は涙を流して告白する――「生涯の最後の二十年間ヴェネツィアで見た異教徒の絵画に影響されました。一時期自分の肖像画をも彼らの手法で描かせたいと望みましたが、恐れました。その後、あなたの宇宙を、僕たちを、あなたの影であるスルタンを、異教徒の手法で描かせました」。
するとアラーは次のように応える。
これは東と西の宥和などというものではない。「私は前でも後ろでも楽しみたいだけ、東と西の両方でありたいだけなのだ」と「咄し家」は歌っていたではないか。「咄し家」のコンテクストでは、「東も西もアラーのもの」とは、「東も西も男のもの」ということである。つまり、「男も女も男のもの」なのだ。女の服をつけ、女になり、鏡に映った〈女〉に向かって勃起した思い出を語る「咄し家」の挿話は、〈女〉が男の作り物でしかないこと、女らしさが幻想であり、男の夢である――「女は存在しない」――ことを、男だけが「東と西の両方であり」うることを端的にあらわしている。
パムクにおいて政治的なものは口実に過ぎない。同様に、細密画師の世界もまた、彼にとっては素材であり、彼が現実に属する国の文化や過去の歴史に取材していることは偶然に過ぎないのだ(むろん、すばらしい素材ではある)。シェキュレの幼い息子のうち年少の方に、彼は自分の名前を与え、『わたしの名は紅』日本語版序文の結びで、あからさまにそのことに私たちの注意を喚起する。
たぶん、日本の読者は試されているのだろう。訳者はあとがきで、「日本語版への序文にも書いているように」シェキュレもシェヴケトもパムクの母と兄の実名であり、「父親が長く家を留守にした時期があり、母親は再婚を考えたことがあったという。しかしこれらの事実以外は、ほとんど作者の作り話であろう」と書いている(ちょっと挨拶に困る記述ではある)。実際のところ、パムクは自分の実人生を、少年が着る叔母のピスタチオ・グリーンの絹のブラウスやその胸に詰め込む靴下やナプキンのように使っているのだろう。あるいは、フロベールが読者に、ボヴァリー夫人と愛人を乗せた馬車が狂ったように走り回るあいだ、窓掛を降ろした車内で起こっている出来事の代りに描写してみせた、馬車がかすめ過ぎる塀の内側で老人たちが散歩している養老院のありさまが、子供時代にギュスターヴが見た、家に隣接する父親の病院の庭の風景に起源を持っているようなものだろう。
もっとも、アップダイクも「からみあった十二の視点の考案者である作家は、彼の小説の外にも内にもいる。シェキュアの下の息子はオルハンと呼ばれ、彼女の協力を得て、彼がこの小説を書いたのだとわかる」と書いているのだから、騙されるのは日本の読者だけではないのだろう。成長したシェキュレの息子が十七世紀初めにこの小説を書くことは、一五九一年にパムクの父親がペルシアとの戦争に行くのと同様ありえない。芸術家としての作者の“分身”を作中に探すとしたら、それは「咄し家」であろう。政治的犠牲者としてではもとよりなく、彼自身の抑圧された受動性すなわち女性性をもおのが身に引き受けた両性具有性もさることながら、〈女〉になった「咄し家」は、男を求めて「亡くなった父がいろいろな口実の下に家に招んだパシャの息子たちや貴族を、覗き穴から覗き見はじめました。その状況が細密画家の全てが恋している二人の子供がいる小さな口のかの有名な美女に似ていることを願いました」と、なんとシェキュレに言及する。シェキュレが覗き穴から、父を訪ねてくるカラを覗いていることなど第三者が知るはずもないのだが(「咄し家」が覗いていたのは過去のことだから、アナクロニックでもある)、もしかしてシェキュレは、カラも足を運んだコーヒーハウスで演じている「咄し家」のレパートリーの登場人物なのだろうか。そうだとすれば、その相手のカラも――そして「咄し家」自身も――物語の中の存在なのか(第一、今はいつなのか)。「もしかしたら、あのかわいそうなシェキュレの物語をしたらいいのかも。でもちょっと待ってね、水曜日の晩はこの話をすると約束しましたよね。」そう言って「咄し家」は別の物語を話しはじめ、話し終えるが、そこに暴徒が乱入してくる。
もしも暴徒に妨害されなかったら、「咄し家」はシェキュレの物語を語りはじめてしまい、その中には「咄し家」も出てくるのだから、物語はいつまでも終らないことになる。そういう事態を回避するためにも、ここで「咄し家」は殺されなければならなかったのかも(こうした入れ子の無限ループについては、『千夜一夜物語』にかこつけてボルヘスが書いており、パムクも読んでいるにちがいない)(☆5)。しかし、「咄し家」は本当に殺されたのだろうか。最終章で、「絵には描けないこの物語を、もしかしたら、言葉には書けるかと思ってオルハンに語った」とシェキュレは言い、「もしカラを実際よりもぼんやり者だとか、わたしたちの生活を実際よりも大変だったとか、シェヴケトを悪く、私を実際よりも美しく恥しらずに語っているとしても、オルハンの言うことを決して信じないでください。なぜなら彼は物語を面白く説得力あるようにと、どんなうそでもためらわないのですから」と読者に呼びかける(これが小説の結びでもある)(☆6)。アップダイクのレヴューのサブタイトルは、「十六世紀の探偵小説がトルコの魂を探求する」とほとんど「美しい日本の私」であるが、「トルコの魂」も「美しい日本」も、作り物であるのはいうまでもない。その技巧を凝らした精緻な細工にこそ作家は細密画師のように心血をそそぎ、「どんなうそでもためらわない」のだ。
ところで、これは本当にシェキュレが語っているのだろうか。もしかしたら、コーヒーハウスで美しいシェキュレの絵(あるいはシェキュレとして描かれた美しい女の絵)を傍に、自らの死をも含む物語を「咄し家」が、「私はシェキュレ」と、〈女〉として語っているのかもしれないではないか。
フロベールにとっての患者の歩き回る病院の庭やパムクにとっての不在の父親同様、『わたしの名は紅』の(十六世紀の)宗教的対立も素材に過ぎない。せっかく「咄し家」について書きながら、「イスラム教国で本や小説が置かれている厳しい状況」へ筆を移してしまうアップダイクの短絡ぶりにはがっかりさせられた。エジプトとトルコでは事情が違うだろうに、「イスラム教国」としてまとめられてしまったのではパムクもがっかりしたのではないか。仮にパムクの小説がアクチュアルな問題に結びついて見えるとしても、それは暫くのあいだの話だ。そういうものが消滅したあとにもパムクの小説は残るだろう。そしてそのときにも、「東も西もアラーのもの」という語句は通用するだろう。コーランから採ったもう一つのエピグラフ(ついでに言えばコーランも“素材”である)「盲と目明は同じではない」という句の示すとおり、縁なき衆生にはわからない――遍在するものが見えない――という事態は相変らず存続するにしても(☆7)。
二 傷つく少年
サー・リチャード・バートンのいわゆる“男色帯”(☆8)をトルコからさらに東へたどると、日本の東京の本郷から不忍池へ抜ける途中に弥生美術館のこぢんまりした建物があらわれる。せんだって何度目かにここを訪れた際、高畠華宵の作品に、彼の描く少年に手足に繃帯をしたものがしばしばあったため、怪我もしていないのに繃帯を巻くことが昭和初年の少年少女の間に流行したという説明が付されているのに出会った(晩年の中原淳一が作った人形が、やはり繃帯を巻いた“傷ついた男”であったことが思い出された)(☆9)。「[華宵は]美少年が捕らわれて縛られたり、危機に瀕して傷を負った場面を多く描いています。/清潔さと不屈の精神を持った凛々しい少年たちはまた、不思議な色気を漂わせ、甘美な感傷に包まれています」と説明は続いていた。
この解説のせいで、ミュージアム・ショップで『昭和美少年手帖』〔中村圭子編、河出書房新社 2003年〕を買うことになった。なるほど、同書の華宵のページには「傷つく少年」という見出しもあり、「少年が、捕らわれて縛られたり、大勢の刺客に取り囲まれて刃傷を負ったような場面を華宵はよく描いた。伊藤彦造ほどの緊迫感はなく、ある程度様式化されてはいたが、被虐のエロスというものを華宵も好んで表現した」と説明されている。伊藤彦造については、編者の中村による巻末のエッセイ「日本の美少年絵画」に、「〈...〉彦造は熱烈な愛国主義者であった。第二次大戦中、彦造は少年誌を離れて、国史に題材を取った日本画を描くなど、憂国の士として活躍する」、「彦造の少年の官能性は、闘いに命をかける少年の、死に直面した極限状況によってもたらされたものであった」とある。
そして、華宵については――
|
| 表紙(目次)へ |