
| 中尾根〜炭焼窯跡〜砥石谷/愛宕山//北山 |

|
| 中尾根〜炭焼窯跡〜砥石谷/愛宕山//北山 |

|

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2006.12.23 (土) 晴れ 哲、道
コース: JR保津峡駅〜中尾根取付〜米買道出合〜大岩分岐〜炭焼窯跡〜ツツジ尾根道出合〜表参道出合〜水尾岐れ〜愛宕神社〜地蔵辻〜砥石谷取付〜作業道突止り〜右の植林地を下り作業道(登山道)に出合〜谷出合〜巻道〜分岐(月輪寺道と地蔵辻への分岐)〜砥石谷出合〜梨木大神〜梨木谷林道〜月輪寺道登山口〜大杉谷道登山口〜清滝 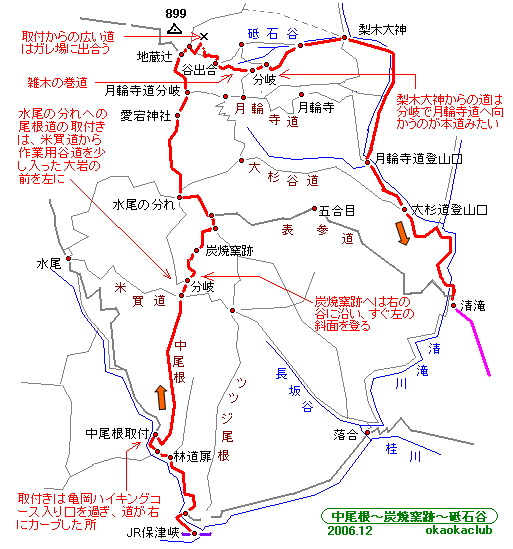
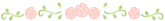
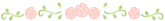
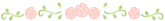
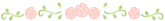
「2006年 最後は愛宕山にしよう」 「今日はハイキングコースの 炭焼窯跡コースと 砥石谷付近を 探索しよう」と出かける。いつもの愛宕山、いつものように遅い出発となり、JR保津峡駅に着くと9時半になってしまう。電車から10名程度の登山客が降り、さっさと出発して消えて行く。「今日は ゆっくりや」と橋を渡り水尾への道をゆっくりと歩いて行くと、車が行ったり来たり師走なのか皆さん忙しそうだ。 亀岡へのハイキングコース入口を過ぎ、右にカーブしている離合箇所の手前にある右の斜面が中尾根の取付である。二人は、ここで上着を脱ぎ、これからの急坂に備える。冬といえど今日は暖かく、すぐに汗をかいてしまう。急坂を登り切ると、尾根までは雑木の間を適当に進んで行くのだが、前回来た時よりテープやリボンが増え、足元もはっきりした踏跡ができていて、最近この中尾根をたくさんの人が楽しんでいるようだ。
尾根に出ると当分の間、シダの道が続き冬枯れの中、緑を楽しませてくれる。この付近はシダに雑木が綺麗で、登っていても心地良い。シダも足元から消えると、疎林の中の登りが続く。取付からシロや黄色のテープが目立ったが、「(サ) H18.12.23」と書いてあり「えっ! 今日や! 先行者や!」と二人は驚く。また歩いていて時々、目に付くテープを見ると「(サ) H18.12.2」「(サ) H18.12.16」・・・「何や この人 毎週 この中尾根を歩いているで!」とこれまたびっくりすると言うか、感心してしまう二人。
勾配も緩くなり見晴らしの良い伐採地を過ぎ、小さなピークを巻くと、すぐに米買道に出合う。米買道を右に進むと新調され木橋が目に止まる。「やっと 小学生の遠足もできるようになった」と道子。この橋を渡らずに、中尾根と橋の中間に北へ入る谷沿いの作業道があり、ここを少し進むと、大岩の手前で分岐している。左に進むと、水尾の岐れに出合う尾根コースだが、今日は右にとり炭焼窯跡を目指す。 谷分岐の小さな枯れ谷を渡ると、道は谷と谷の中間にある小さな支尾根に取り付いている。思ったより左の尾根に取り付いているので、哲郎は地形図で確認する。少し登って行くと、分岐に出合うが目的地はもっと右にあると思い右をとる。それでも哲郎は左の谷に降りて行く道を進み、一応確認する。
斜面の雑木や植林地の中をジグザグに登って行くと、植林地の中の炭焼窯跡に着く。「ここかいな〜」と石組みが少し残った穴を覗き込む。そこから、まだまだ斜面の登りは続き、最後は平坦になり、右手の尾根に曲がっている。前方から声が聞こえてきて、よく見ると植林地の中に人影が見えてくる。表参道七合目からのツツジ尾根への道に出合い、この合流点を何度も確認する。テープはたくさんあるがツツジ尾根を下る場合は、ちょっと分かりにくい。ここは表参道から4〜5分でヒノキの植林を下って、ちょうど平坦になった所である。
表参道に出合うと、たくさんの登山客に出会い、「年末やからな〜 皆さんお札をもらいに きてるんやろ」。昼食は水尾の岐れからケーブル駅跡への道を少し入り、陽だまりの暖かそうな所でオニギリを食べる。昼食後、出発準備をしていると、駅舎跡から夫婦らしき二人連れが通り過ぎる。我々は後を追うように愛宕山神社へ向かう、神社から「下山は 砥石谷にしよう」と参道を後にする。
月輪寺道から砥石谷へ降りられそうだが、今日は地蔵辻からの支尾根を下ることにする。地蔵辻から首無地蔵への道を2〜3分進むと、右の谷に降りるを見つけ「ここから 降りてみよう!」と進入する。少し下ると小屋があり車が通れそうな道が続き「なんで こんなに広いんや?」と思ってしまう。道なりに降りて行くと、石がゴロゴロしてきて、最後はガレ場に出合い道は行き止まりとなる。「随分と 北によってしもた」と言いつつ、ガレ場を下るかどうするか少し考える。 哲郎は砥石のような薄い石がゴロゴロしている植林地を10mほど降りてみて確認するが、その下には雑木が続くヤブがある。「右手の 植林地を進もう」と道子に降りるように言う。ケモノ道を見つけ植林地を右に進み、支尾根に近づいた所で、植林地を降りて行く。植林が途絶えた所で、道子は左の雑木林を、哲郎は右の植林地の端を調べる。哲郎は植林地の端に上から続いている作業道を見つけ道子を呼ぶ。「これが 地蔵辻から 砥石谷への道や!」と二人で確認する。この上はどうなっているかは宿題として、この道を下りて行くと、すぐに枯れ谷に出合う。この谷に沿って降りて行ってもよいが、谷を渡った向こう側の斜面に、立派な巻き道が続いているので、今日はこの道を進むことにする。
雑木の中、快適な巻き道が続き、途中で谷が石で埋まった細い谷に出合う。この谷を渡たり進んで行くと、次の支尾根で右上からの道に出合う。上の方にたくさんのテープがあるので、この道が月輪寺への道と確認する、ここも宿題として今日は砥石谷へと下って行く、道は植林の中へと変わり、谷に近づいてくると急な下りに変わる。左に谷の合流を見て、しばらくして谷へと降りて行く。 あとは谷沿いに進み谷を渡って行くと、すぐに梨木大神のある梨木林道に出合う。「あ〜 やれやれ」と小休止しながら橋の向こうある小さな谷への入口にテープを目にする。「たしか この付近から 月輪寺へのルートがあるんや」と哲郎。近づいてテープを見ると「(サ) H18.12.23」とありまたまたビックリ。なんと(サ)の人(マルサの男)は途中ルートは分からないが、中尾根から梨木大神まで、我々と一緒である。
ブラブラ歩く梨木林道、「マルサの男性は どんなルートをたどったのだろう?」と考えながら清滝へ向かう二人。「マルサの女は知っているが マルサの男か!・・・」。 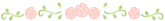
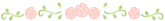
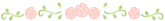
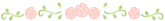
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||