
| 愛宕山(岩ケ谷〜梨木大神)//北山 |

|
|
両岸に絶壁の岩が迫るが、ここには 古道が残っていて難なく歩ける岩ケ谷 |

|

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011.07.09 (土) 晴れ 哲、道
コース: 水尾バス停〜岩ケ谷取付〜猪ケ谷コース分岐〜(岩ケ谷遡行)〜標高700m付近から植林地の作業道を登る〜岩ケ谷源流〜お墓〜ジープ道出合〜愛宕山三角点〜地蔵辻から首無地蔵への道〜標高760m付近から右手の斜面を下る〜梨木大神〜梨木谷〜清滝バス停
注意:
岩ケ谷の古道、谷に接している部分はほとんど崩壊しています。その為谷の中や谷横の斜面を通ることになりコース選択が必要なので、初心者危険コースとします。迷うことはありませんがコース全体に小さな滝が連続し、V字の谷でエスケープルートはありません。 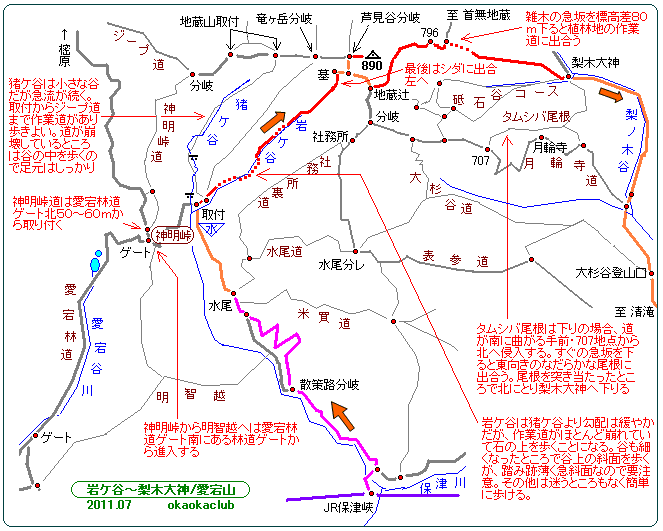
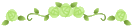
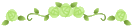
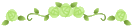
京都地方の梅雨も明け、今日は35℃の猛暑日との予報だが愛宕山へ出かけることにする。目的は愛宕神社西方に流れる岩ケ谷の再調査である。「暑いので」とJR保津峡駅から水尾へのバスを利用することになり、JR京都駅7:40発の電車に乗る。 早朝のJR保津峡駅に4名が降り立ち、3名がバスに乗る。他の1名はツツジ尾根へ向かうようだ。バスはスイスイと進み、10分足らずで水尾へ付き、サービスだろうか登山口への道の前で降ろしてくれる。登山者はすぐに登山口へと向かうが、我々は目の前の建物(農協と書いてある)を見ていると、折り返してきたバスの運転手が「ここはお昼からですよ!」と教えてくれる。我々は集落を抜けるように北へと歩き始める。
集落を抜けると柚子畑が続くが、その木の下にたくさんのオオルリソウを見て「なんや、こんな所に沢山咲いているやん!」と哲郎、右の石垣に鈴なりのキイチゴを見つける道子、「花よりイチゴ!」と二人は手を伸ばし早朝から道草のようだ。このイチゴはナワシロイチゴのようで、散々食べておいて「前回、愛宕道で頂いたモミジイチゴの方が美味かった」という結論になる。 柚子畑を抜けると谷上の高い所を歩くようになり、周囲は植林地と変わる。左下に勢いよく流れる谷が見えて来ると岩ケ谷取付はもうすぐだ。前方カーブミラーが見えて来て、そこが取り付きなのだが、その手前数10mにある水場で小休止し冷たい水を頂く。
岩ケ谷取付に来てユックリと準備する。今日はバス利用で早く来たつもりだが、ノラリクラリで結局登山開始は9時となる。早速作業道を歩き始めるとすぐに猪ケ谷コースの分岐に出合う。今日は岩ケ谷なので、ここを谷に沿って直進する。 すぐに谷横の植林地を歩くようになるが、道は打ち枝で埋まり荒れてきてはっきりしなくなる。それでも、谷のマイナスイオンと谷の流れの音を聞きながら歩くのは心地よい。
道は次第に谷水で洗われ消えて来ると、足元に石がゴロゴロしてくる。標高350mで谷に突き当たり対岸へ渡る。丸太の橋がかけてあるが、道子は「滑って怖い」と谷の中を渡る。 対岸(左岸)へ渡ると右手に植林地が広がり谷沿いにケモノ避けネットが続く。そのうち雑木の下を歩くようになり、いつの間にかネットから離れる。
雑木を抜けると再び植林地が見えて来て、右手にネットが見えてくるが、右手の斜面がきつくなり標高400m付近で右岸へ渡ることになる。 渡った右岸には谷沿いに古道が残っていて、難なく歩くことが出来る。地形にもよるが、古道は流れの緩やかな所や少し高い所にあれば残っていて、急流の谷傍にあれば洗われて消えているようだ。谷が少し急になって来たところで道は再び消えてくる。
目の前に大きな石がゴロゴロした谷を見る。前回は右手の植林地の斜面を歩いて行ったが、荒れていて歩けそうも無いので、谷中の岩や石の上を歩いて行き、植林地が歩けそうになった所で植林地へ移動する。植林地に道のようなものが現れてくると、前方に数mの滝のようなものが見えて来るが、登って行くと、それは階段状の小さな連続した滝である。
左岸の古道もはっきり、しっかりしてきて、緩やかになった谷沿いを歩いて行く。しかし数分も歩けば谷も急になり、道も消える。前方左手に絶壁の岩が迫り、右手の植林の奥にも絶壁の岩が続く。「えらい所や!」と思ってしまうが、そのわずかの斜面にも植林がしてあり、「こんな所までしなくても」と哲郎。 左岸が詰まったところで渡渉し、両岸の絶壁を見て「前回、何処を歩いたのやろ?」と思ってしまう。右岸を進んで行くと絶壁の下に古道が現われてくる。
古道は石を積み重ね谷より高い所に造ってあるので大水にも耐えているのだろう。一箇所崩れかけて谷を渡り返すものの立派なつくりである。数分で絶壁の下を抜けると植林地が見えてくる。谷が急になって来たところで道も次第に消えてきて、雑木に変わると道が消え、斜面の少し高い所を歩く。 数mの滑滝右手に見て、少し進むと左上の植林地の中に道を見つけ、道へ上がる。高い所の古道は残っているもので、楽に歩くことが出来る。このコース数分毎に状況が変わり、「これが楽しい!」ということになる。
炭焼窯跡を過ぎると、緑に苔むした谷傍を歩くことになるが、「あっ!」と昔を思い出した哲郎は先を行く道子を呼び返す。この谷は標高650m付近から伏流となるのだ。ここで小休止とし、冷たい水で顔を洗う。 この先はゴロゴロした枯れ谷、でも今日は全体に水量が多いのか表面にも少し流れている。そんな横を登って行くと標高700m付近で枯谷を渡り、左岸の植林地の道を登ることになる。
植林地の作業道は古道であろうか、一直線に登って行く。急勾配の道、それも一直線で標高差80mも登ることになり、さすがに途中で小休止することになる。ふと目の前の木を見ると高い所に「熊出没注意」の注意札を見る。 急坂を登り切ったところで広い道は消え、左手にある細い谷に沿って北寄りに進んで行く。この谷は岩ケ谷の源流で、細くなっているが水が流れているので、この水で顔を洗う。
低木の植林地を登って行くと、明るくなったシダの群生地に出合う。前回来た時よりシダが少ないが、左上に道のようなものが見えるので、「着いた!」と道子に言い、一登りしてお墓の取付道にでる。もう11時を回っているので「岩ケ谷、2時間の谷遡行」となる。 「お昼だ!、三角点へ向かおう」と、取付道からジープ道に出合うとたくさんの登山客に出会い、「夏の愛宕山も人気やな〜」と感心してしまう。三角点近くの風が当たる所でお昼とする。
「折角、愛宕山へきたのだから、下山も再調査コースを」と、今日は梨木大神への急斜面コースを下ることにする。地蔵辻から首無地蔵への道を進むと左手に谷の源頭を見る。その先の「・796」を過ぎると登山道は下って行き北向きに変わる。そして左手に再び降りていけるような谷の源頭を見る標高760m付近、その右手が梨木大神への取付である。 登山道にはマークが無いが、登山道の右手(東)がちょっと広くなっているのですぐに分かる。その一角に下りて行く踏跡があり近くの木にマークがある。早速、雑木の急斜面を下り始めるが、最近色々と急斜面を下っているので、道子もここの斜面が以前ほど急斜面とは感じないようだ。
雑木の踏跡はジグザグに下り、マークも増えたくさんの人が利用しているようだ。標高差80mも下ると植林地に出合、右端へ寄って行くと作業道があり、それをジグザグに下って行く。標高差100m近く下って行くと、道は植林地から雑木に変わるが、はっきりとした作業道が続く。雑木の中を標高差100m以上下ったところで植林地に出合、下に梨ノ木谷を見ながら下り、最後は梨木大神近くの砥石谷に降り立つ。
標高差400m弱を1時間での下降であったが、これが遅いのか、速いのかは分からないが、最初の雑木で変な所へ迷い込まないかぎり安全なルートでお勧めです。梨木谷へ降り、二人はユックリと涼をとる。梨木林道で人に出合うことはほとんど無いが、月輪寺登山口を過ぎる頃から他の登山者に混じって、ユックリと清滝バス停へ向かう。 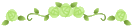
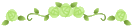
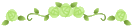
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||