
|
愛宕山(ケーブル軌道跡〜中尾根)//北山 2011.03.12 |

|
| 静かなケーブル軌道址を楽しむ |

|

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011.3.12 (土) 晴れ 哲、道
コース: 清滝バス停〜金鈴橋〜ケーブル駅跡〜5合目へのジープ道横断〜ケーブル山頂駅舎〜水尾の別れ〜大岩〜中尾根〜車道出合〜JR保津峡駅 注意: ケーブル軌道跡コースでは、3、5号目のトンネルが崩壊しています。ここは危険なので、中に進入せず右手の斜面を登り迂回して下さい。 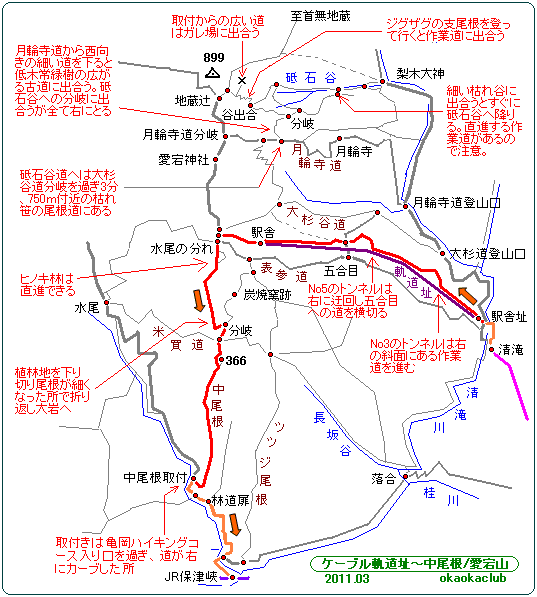
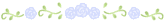
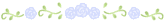
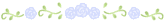
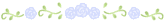
今週は比良へ出かけ雪を楽しむ予定であったが、前日発生した東北の大地震、「とても、雪を楽しむ気になれない!」と中止する。それでも、落ち着かない二人は、「愛宕山でも」と出かけることにする。 JR京都駅から清滝行のバス、ダイヤ改正され本数が少なくなっている。8時23分発のバスに乗り、清滝へ向かうが、嵐山へ来ると左に折れ、渡月橋を渡るので「???」。阪急電車に接続するようにルート変更され、「阪急電車利用の方が、接続が多くて便利や!」と道子。 バスが清滝バス停に着くと、すぐに登山口へ急ぐ皆さん、でも今日は地震の影響か登山客は少ない。金鈴橋を渡ると、目の前にこんもりとした丘がある。階段を上って行くと広場があり、まさしく、ここがケーブル駅舎跡なのである。コンクリート製の階段状の乗場が残っていて、その上でゆっくりと準備する。服の調節も終わり、階段状の軌道を歩き始めるが、今日は暖かく、すぐに上着を脱ぐことなる。
しばらく表参道に接して歩くことになるのだが、ケーブル軌道の方が低くなっているので、お互いに顔を見合わせるようなことはない。この付近は軌道の両側に石組みが高く積まれ、壁になっているので左右の視界は悪い。軌道に壊れた所はなく、以前と同じようにスイスイを歩くことができ、すぐに最初のトンネル入口に着く。前方の出口が明るく見えるので、「大丈夫や!」とトンネルの中を歩いて行く。でも途中で暗くなるので、ストックで段を確認しながら歩いて行く。
トンネルを抜けると、もう周囲は植林地、すぐに次のトンネル入口に着く。ここも「大丈夫だ」と通り抜ける。軌道の両側には植林地が広がり、特に素晴らしい景色はなく、ケーブルが動いていた頃には、「どうだったのだろうか?」と考えてしまう。3番目のトンネルの前には、赤ペンキで「×3」と書いてあり、通行できないことを示しているようだ。小休止しながら左右の植林地を見る。どちらも登れそうだが、右手に踏跡が続いているので、ここを登ることにする。
すぐに立派な作業道に出合い、斜面を大きく巻いて行く。巻き道がはっきりしなくなる頃、左上に軌道が見えてきて、一登りすると軌道に出合う。軌道ばかり歩いているより、変化があって迂回路もいいものだ。4番目のトンネルは幅が広く、大きなトンネルである。中を歩いていると、軌道が増えてきて出口へと続く。ここは上下のケーブルがすれ違う所で、先を行く道子に言うが、関心がないのか、スイスイと先へ進んで行く。 軌道は所々高架になっていて高い所もあるので、高い所が苦手な人は、中央付近を歩いた方が良いだろう。5番目のトンネルがやってくる。このトンネルも通れないので、右手の斜面を登って行く。ここは急斜面、踏跡を辿って登って行くと、黄色い境界マークの所で作業道に出合う。またまた快適な道が続き、大杉谷から表参道5合目へ通ずる広いジープ道に出合う。
この広い道を横切った所に、細い作業道が続いているので、我々はその道に進入する。最後、道が怪しくなった所で、前方に大きな階段状のコンクリートの構造物を見る。「何んだったかな、これは?」と横を通り過ぎ振り返ると、それはトンネルの出口であった。ここは我々が、以前最初に軌道に出合ったポイントで、大杉谷から水尾の別れへ向かう時、分岐を左へ右へとり、ここに辿り着き軌道に出合ったことを思い出す。
この付近は高架が多く、所々に積雪もあるので注意しながら登って行く。白い雪の上に「二人の足跡がある」と道子、どうやら、今日、このルートに先客があったようだ。最後のトンネルを抜け小休止するが、もう標高600mを過ぎているので、じっとしていると寒く感じてくる。標高650mを過ぎると、前方に駅舎が見えてきて、「もう少しや!」と言うものの、駅舎はなかなか近づかない。やっと駅舎の形が見えてくると、「やれやれ!」と言うことになる。
軌道から上り駅舎の中へ入る。もういつ崩れてもおかしくないようなボロボロの建物で、もう何十年も風雨にさらされているが、「なかなか倒れないものだ」と感心する哲郎。駅舎を後にして、水尾の別れからの取付道を歩き始め、「ここは暖かい!」と途中で昼食休憩とする。この付近は遊園地があったようなのだが、それはもう遠い昔のことのようだ。昼食後は水尾の別れに向かい、目の前に白く染まった表参道に出合う。
水尾の別れには、水尾からのバスの時刻表が掲示してあり、遅くなった時や、しんどい時は利用するとよい。我々は下山ルートを中尾根とし、休憩小屋から水尾へ下った道の、すぐ左の植林地へ進入する。取付にはマークがあるものの、途中ヒノキの植林で細い枝が密集している。枝がない所がルートなので、前方を確認しながら下って行く。ほぼ真っすぐに下って行き、植林を抜けると疎林が広がっている。そこには細い踏跡が続いているので、尾根を外さないように下って行けばよい。 しばらく下って行くと、道がはっきりしてきて、そのうち植林地に出合う。左手に大岩が見えてくると、折り返し少し下ると、大岩に出合う。岩にはピンクのペンキでマークがしてあり、スミヤキ窯跡コースへ続いているようだ。ピンクは目立つが「ペンキはあかん!」と哲郎。作業道を谷沿いに下って行くと、すぐに米買道に出合う。「米買道が、整備されました」と新聞で読んだことはあるが、この出合った地点に「大岩」の立派な標識を見る。
米買道を水尾へ10mも歩けば、中尾根の取付に出合う。少し登って尾根に乗り、ゆっくりと下って行く。ピークを巻いた植林地を過ぎると、雑木の尾根が続く。しばらくして明るい伐採地に出合うが、もう雑木が伸びてきて緑一杯になり、木の成長の速さを感じる。雑木の尾根は次第に下って行き、足元にシダが増えてくる。時々咲いているアセビの花を確認しながら下って行き、勾配も緩くなる頃、緑のシダの中を歩くようになる。「ここはいつもきれいや!」とシダと緑を楽しみながら下って行く。
下り切った所で、シダの中で道が幾つにも分かれた所があるので、左右をとらずに尾根を進む道をとる。しばらくして道が怪しくなる頃、右下へ下りて行く道があるので、ここはゆっくりとルートを選定しよう。この中尾根、たくさんあったテープは一掃され、スッキリとして心地よく歩くことが出来るが、この下降点だけは分かりにくいので注意が必要だ。雑木の中、急斜面を下って行くと、ロープが張ってあり「助かる」と道子は喜ぶ。 前方に車道が見えてきて、すぐに降り立つ。目の前の電柱を見ると、「ミヅオ 93」と書いてある。JR保津峡への道を歩き始めると、すぐに鉄のゲート「地形図 ・94」に出合うのだが、「え〜!」と二人、そこにゲートはなく、道路を広げる工事をしていて、山を削り立派な壁を造っている。
JR保津峡に着くと、ちょうど14時、すぐの電車があるのだが、ここは一本遅らせて、ゆっくりと後始末する二人。下に流れる保津峡もまだ冷たいのだろう、もう始まっている保津川下りの舟は見ることもなく、ひっそりとしている。 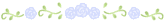
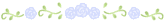
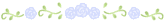
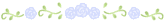
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||