
|
愛宕山(八丁山南尾根〜竜ヶ岳)//北山 2010.04.10 |

|
| 八丁南尾根から八丁山へ登る |

|

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010.4.10 (土) 晴れ 哲、道
コース: 清滝バス停〜月輪寺/東海自然歩道分岐〜堂承川分岐〜八丁山南尾根〜八丁山東尾根出合〜ヤカン(・473)〜八丁尾根〜首無地蔵〜竜の小屋〜芦見谷分岐/竜ヶ岳登山口〜竜ヶ岳〜ジープ道出合〜愛宕神社境内〜水尾の別れ〜水尾〜水尾バス停 注意: ■八丁山南尾根は標高200mより下に踏跡はなく、急斜面が続きますので、初心者危険コースです。 ■堂承川から南尾根に取り付く場合、東寄りに巻いて行く古道を登って行き、急な斜面が切れた所にある分岐(薄い踏跡)から、左に折れ踏跡を辿って行きます。登って行くと、標高155m付近から薄い巻き道に出合い、巻き道からすぐに、尾根に向かって斜面を登って行きます。 ■この取付周辺のピンクとオレンジの太いテープは、ケモノ用のTRAPが仕掛けてあるというマークであり、登山用ではないので近寄らないで下さい(危険)。 
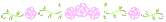
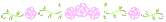
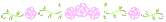
おばさん山歩き隊によると、「愛宕山にコバノミツバツツジが咲いている」とあり、「コバノミツバツツジを見よう!」と道子、結局、今日の山行きは愛宕山となる。「折角だから、八丁山南尾根の取付を、探索しよう!」と、例年行く明智越やツツジ尾根は「帰りに寄ろう」と言うことになる。 JR京都駅7時37分発の清滝行のバスは、早朝にもかかわらず登山客が多く、「もう春なんだ」と思ってしまう。何処かの登山グループか、嵐山バス停からも大勢乗ってきて、久し振りにバス内は賑わっている。 終点の清滝バス停で降り坂を下って行くと、丁度サクラが満開で、こちらの方も賑わっている。「準備は八丁南尾根の取付で」と橋を渡り東海事前歩道を歩き出す。月輪寺道分岐に来ると、目の前にコバノミツバツツジが咲いていて、この花を見ながら準備する。準備も終わり堂承川への階段を下りて行くと、目の前の川、今日は水量が多く「何処を渡ろうか?」ということになる。
やっと渡れそうな所を探し渡渉する。今日の目的は「八丁山南尾根の下からの取付を探索する」であり、早速尾根の東側にある古い作業道を登って行き取付を探す。左側の斜面を見ながら数10mも登って行くと、斜面の雑木にピンクの太いテープを見る。登れそうもない斜面、「なんで?」と哲郎。少し進むと左手に枯れ谷のような所に薄い踏跡のようなものを見つけ、哲郎はちょっと進入して調べる。「行けそうや!」と取付で待つ道子に言い、今日はここから登ることにする。
途中で緑色のテープを見つけ左手に登って行く。その右手に再びピンクの太いテープ「このピンクは変な所を登っているな〜」と哲郎が近づいて確認すると、そこにはTRAPがあり、どうやらピンクのテープはTRAPを仕掛けたマークのようである。標高150m付近まで登ると、これまた薄い巻き道に出合う。この道を左へと進んで行くと再びピンクやオレンジの太いテープがあり、今度は踏跡のある道にTRAPを見る。 先に進む道子に引き返すように言い、再び巻き道の合流点でこの先のルートを考える。結論は「ここから尾根まで斜面を登っていこう」ということになり、斜面の登れそうな所を選びながら登って行く。そのうち石がゴロゴロした尾根に出合い、標高170m付近で前回下りたときに付けたマークを目にする。
「これで、いいんだ!」と尾根を登り始める。尾根にはコバノミツバツツジのピンクが増えてきて、標高200m位から尾根の道もはっきりしてくる。「あ〜やれやれ」「ここまで1時間もかかってしもた!」とたくさんのピンクの花で賑わう尾根で小休止する。もう今日の探索は終わったようなもので、後はピンクの花を見ながら八丁山へと登って行く。 石柱の境界マーク「26」で右からの道と出合い、尾根を登って行くがなかなかヤカンまで到達できない。「ここは下るのは速いが、登るのはしんどいな〜」と思っていたが、今日は4月とは思えないような暑さで、しんどいのかも知れない。道子は「お腹すいた〜」と言うが、ヤカンまで登り切ることにする。登りが緩やかになる頃、八丁東尾根の道に出合い、左にとりヤカン(P473)に着く。
ヤカン11時30分、「ここは殺風景だな〜」と八丁尾根を進むことにして、結局八丁尾根の植林地が切れる所まできて昼食とする。ここは標高500mを過ぎ、谷山林道へ直登する手前である。昼食後は林道まで標高差100mの斜面を登る。この道は踏跡もはっきりしてきているので、たくさんの人が八丁尾根を歩いていることが分かる。登って行くうちに右手の雑木が刈り取られ「植林でもするのやろか?」と殺風景な道を登って行き、やっと谷山林道に出合う。
「遅くなったな〜」と、この先のルートは首無地蔵で決めることにして、林道をユックリと登って行くと前方から二人の男性が降りてくる。少し年配の二人だが足取りもよく、「今から西ノ谷を下り高雄山へ行く」と言っている。その周辺はokaokaclubも周知したエリアなので、話も弾み20分も話し込んでしまう。「遅くなってしまう」と話を切り上げ、元気な二人と別れる。「彼らは八丁東尾根を下り西ノ谷口から△428へ向かうようだ」と哲郎。 首無地蔵の駐車場から愛宕の山々を眺めるが、目の前の斜面にタムシバが咲いている。タムシバは高い所に花を付けるので、上から見下ろした方がよく見える。首無地蔵13時15分、「遅くなるかも知れないが、竜ヶ岳へ行こう!」と久し振りに芦見谷へと下って行く。谷に出合うと茂っていたササが枯れていて、源頭へ続く細い谷にはクリンソウの株が続き、「これだけの株がそろって咲けば、京都の花100選になってもいいかも」と哲郎。
竜の小屋では珍しくグループがいて、何やらトレーニングをしているようだ。そんな傍を通り抜け、谷分岐にある竜ヶ岳取付に着く。ここもスッキリと明るく、雑木に覆われていた以前の面影は無い。山頂まで標高差300m近くあるのだが「山頂まで30分や!」と哲郎、「そんなん無理や!」と道子。今朝の八丁南尾根の取付で100m登るのに1時間かかってしまったが、ここはそこよりも急斜面だが足元がしっかりしているので二人ともスイスイと登れる。
さすがに「疲れる」と、途中で小休止するが難なく登って行ける。標高800mを過ぎ、しばらくすると登山道は右の斜面を巻いて行く。「昔は真っすぐ登っていたのに?」とボンヤリと覚えている哲郎。北側の尾根に達すると、その尾根を登り始める。やっと竜ヶ岳の山頂に着き、しばらく周囲の景色を楽しみながら小休止し、南の尾根を歩き始める。この尾根は雑木が多く「タムシバでも咲いているだろう」と期待してやって来たが、花も緑もない冬枯れの道が続く。 尾根には900m前後のピークが幾つもあり、探索で疲れた二人には、「ちょっときつい」ということになる。「タムシバはどこや!」と尾根から周囲を見渡すと、どうやらタムシバはもっと低い所で咲いているようだ。やっとジープ道に出合い左にとり愛宕神社を目指す。もう遅いのか人には出会わず神社の境内に着き、自動販売機でスポーツドリンクを買うが、「300円とは伊吹山より高い!!」。
それを飲みながら下山ルートを考えるが「遅くなるが、ツツジ尾根にしよう」と水尾の別れへ向かって歩き始める。ユックリと下って行く表参道、まだ登ってくる数人に出合い水尾の別れに着く。目の前にある水尾のバスの時刻表を見て「16時20分、これにしよう!!!」と道子。「今15時30分や間に合うやろか?」と周辺の標識で下山時間を確認すると水尾まで「40分」とある。
ギリギリ間に合うだろうと二人は急いで水尾道を下り始める。この道はよく手入れされていて、二人は走るように下り30分で登山口に着く。登山口には「バス停まで6分」とかいてあり、「もう間に合うだろう」と目の前の満開のサクラを見ながらユックリと下りて行く。定刻にやって来たバスに乗り「いつも綺麗や!」と水尾のサクラを満喫しながら、二人はJR保津峡駅へ向かう。 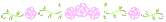
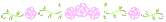
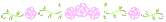
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||