
| 愛宕山〜地蔵山 (小てつ NO.62) |

|
| 地蔵ピークは大繁盛 |

|

|
||||||||||||||||||||||||||||
|
平成26年7月27日(日) くもりのち雨のち晴れ 小てつ単独
コース: 越畑〜芦見峠〜芦見谷川林道〜竜ヶ岳東尾根登山口分岐〜愛宕山三角点〜地蔵山〜芦見峠〜越畑 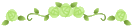
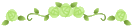
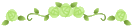
今週は連日の猛暑日が続き、少し体を休めたら?という嫁のやさしい声もあったが、週に一度は仕事でない汗をかかないとおかしくなりそうなので、天気予報もかんばしくないことから、近場で涼しいところはないだろうかと思案して、登りを芦見谷の遡行として涼しく稜線まで登ろうと、先述のコース取りを考えました。 いつものように稲妻号で7時に家を出発し、近くのコンビニでおにぎりを仕入れて、愛宕寺前でヘアピンに曲がり、平野屋の前でまたヘアピン、六丁峠に向かう。JR保津峡駅を越え、水尾の里も神明峠も超えて、宕陰小中学校の脇までたどり着く。学校の正門脇に路肩が小広くなった場所があり、普段は学校の先生の駐車スペースになっているのだが、今日は夏休み最初の日曜日と言うことで、まさか先生もお休みだろうと、それでも端っこの方に置かせていただく。丁度8時に出発できた。 登山靴にだけ履き替えて、学校脇の石碑のところから取り付く。ここから取り付くと、ほぼ水平に歩いて行ける。ただ民家の裏手やすぐ脇を通ることになるので、住民の方と遭われたら挨拶くらいはして欲しいところだ。いくつか分かれ道があるが、ほぼまっすぐに民家を抜けていくと、立派な石垣の積まれた家に行き当たる。 以前、この立派な石垣に赤ペンキで矢印をした不届き者がいて、見るたびに同じ登山者として心苦しい思いをしていたものだが、ようやく赤ペンキの跡もわからなくなり、そのかわり地蔵山への標識が建てられていた。
石垣の家のあたりにだけ季節の野草があり、やはり花も人を選ぶのだと思ってしまう。でも毎年越畑のジャンボかぼちゃを育てておられた畑に、今年はかぼちゃの姿は無かったのは残念。
鹿よけのフェンスのカンヌキを外してワイヤーメッシュの扉を開けて進入し、扉を閉じて再びカンヌキをしておく。すぐに林道が新しく切られていると感じた。十字路になった林道の新しい方に進んでみる。以前は古い方の水路が脇にある方に進んだのだが、見るからに荒れていたからだ。新しい林道に進んだ方が正解で、前の林道はすぐ先で崩れていた。ところが、新しい林道もそのすぐ先で崩れていた。ここが以前愛宕中毒患者のFさんの情報にあった去年の大雨で崩れた場所だった。現在では、崩れた場所の脇の斜面にロープでガイドされた迂回路が作られており、難なく歩ける。 崩れた場所のすぐ先に越畑隧道の出口があり、そこは無事で安堵する。いつ見てもよく掘ったものだと感心するトンネルだ。もっと大きければ堀り方も想像できるが、こんな小さなトンネルだとそれこそ映画「大脱走」バリの仕事だったろうことを考えると、閉所恐怖症の小てつは震えあがってしまう。
そこから一汗かいて芦見峠に着く。今日はそのまま峠を乗り越して、芦見谷林道に降っていく。峠からすぐに道は三つの分岐になるが、左は三頭山、右は昔の水路跡で今は先で崩れてしまっている。真ん中の道を進む。せっかく登ってきたのにもったいないが、50mほど降ると林道が見えてきて、降り立ったところが越畑隧道の取水口。コンクリートの橋まで戻って、林道を右手に進む。
林道ではあるがすぐそばに流れがあるので、いくぶんひんやりと感じる。やはり今日はこのコース取りで正解かも?と思うが、林道を進むにつれ遠くに雷鳴が聞こえ、ふってくるなら山道に入ってからにして〜と思う。 林道はいたるところに崩れた場所があり、バイクのタイヤ跡はあるが、車の進入は全く出来ない状態になっている。これだけ崩れた場所があって、斜面に埋まっていた石が流れ出しているが、オヤジ殿が興味をしめす石はないんやろうな〜といつも眺める。 天気予報通り、9時まえにポツポツしだして、すぐに本降りとなってきた。丁度滝谷の沢合流地点くらいだったので、林道終点までもう少しというところ、カッパは着ないで、ザックにカバーをし、折りたたみ傘だけさして歩く。雷鳴もなくなっていたし、カッパを着ると逆に汗で内側からビショ濡れになりそうだ。林道だから引っかかるものもないし、傘のえをザックのチェストストラップに差し込んで腕組状態で歩く。9時20分に林道終点に到着。 案の定、山道に入ると木が雨つぶを和らげてくれるので、結局そのまま傘差しのままで歩くことにする。竜ヶ岳東尾根登山口分岐に着き、沢水で顔を洗って涼をとり、愛宕三角点に向かって芦見谷川の遡行ルートに入る。徐々に雨は小降りとなってきて、これまた予報通り。空が明るくなってきて、稜線に出る頃には止みそうな雰囲気となってきた。 この谷はほとんど昨年の大雨の影響は無かったようだが、一ヶ所だけ、斜面がえぐり取られた場所があり、上から降りてくると間違わないのだけど、下から登っていくと、崩れた岩肌に導く踏み跡があり、そっちに引っ張られると怖い思いをしなければならないので、おかしいと思ったらいったん引き返すことだろう、高巻きの安全な道がある。 稜線の方では、かなりの降り方だったのか、沢の水がにごり出した。これでは水場の水もくんで帰れないなぁと残念に思っていると、周りに虫が出だした。忘れていた・・裏愛宕は虫が多いんやった。 今年はあちこちで小バエが大発生ということだけど、裏愛宕は前から虫の多いところだと思う。ハッカ油とプレシャワーを帽子からザックからかけまくる。 ところが、時折チクッと刺す奴がいて、そこは容赦なく叩いて潰す。首にかけていたタオルも武器にして、振り回して撃退する。他の山ではこのチクッと刺すアブはあまりお目にかからないが、愛宕では良くやられる。ただ、富山県にいるような血液を吸いにくる「オロロ」と呼ばれる怖い奴じゃなくって、汗を吸うのを目的にしているアブなんだろうが、気持ちの良いものじゃないから。そのうち、スズメバチに擬態したスズキナガハナアブがやってきた。ブーンといかめしい羽音だが、本当のスズメバチほどの迫力はないし、いつまでもしつこく周りを旋回するのは奴に違いないと、タオルで撃墜すれば、案の定そうだった。 。
三角点下の水場まで来ると、例の刺すアブが3、4匹も飛んでいるので、最後の水場と、顔だけ洗って退散する。水場のすぐ上で、緑のカエルがはねるので見てみると、黒い模様の無いカエルだったから普通のアマカエルではないようだけど、マダラ模様もないのでモリアオガエルでもないようだし、ひょっとするとシュレーゲルアオガエルかな???三角点は独り占めだけど、ガスで何も見えず。そそくさとジープ道まで降って地蔵山に向かう。ここまで、出会ったのは、芦見谷林道ですれ違ったトレランの男性一人。やはりこの天気じゃ登山者はなく、ガスで見晴らしもない稜線の道を地蔵山に向かって静かに歩く。 ところが静かだと思って反射板のあたりまで来ると、賑やかな話声が聞こえてきた。男女2人ずつのグループとすれ違う。本格装備で、山なれした人たちと見受けた。と、すぐに男性7人のグループとすれ違い、地蔵ピークに着くと男女10人ほどのグループが休憩中だった。何と今日の地蔵山は大盛況だ。 ピークで休憩中だったグループの女性が、愛宕神社は人が多かったかと聞いてくるので、神社にはよっていなくて、愛宕に来てもまず行きませんと答えると、今日のコース取りを聞いてくるので、解説するのだがあまりピンとはこないようだった。 10人グループは、小てつと入れ替わるように愛宕に向かわれた。普段のように静かになった地蔵ピークで、ラーメンタイムとする。今日は早く出来るチキンラーメン。チキンラーメンは早くできて良いのだが、なぜか冷めるのが遅いようで、スープを飲み干すのにしばらく置いておかないといけないくらいだ。
ラーメンタイムを終え、ピークをたとうと西向き地蔵方向に進むと、防獣ネットの方に、夏みかんの皮が捨ててあるのが見えた。まだ新しかったからさっきのいずれかのグループの仕業だろう。なんでこんな悪天にまで山登りするくらい山好きなのに、ゴミを捨てていくのか理解できない。自分の後には誰も来ないとでも思っているのだろうか?。 西向き地蔵まわりのアセビが大きくなっていて驚いた。すぐにアセビのジャングルになってしまうんだろうな。とか思って降っていると、またガスが出だして幻想的な景色となる。 スキー場跡まで降りてきて、売店跡に行ってみると「ミッション・コーラ」の看板が、訳のわからないブリキ板になってしまっていた。
芦見峠手前の植林が伐採されていて殺風景な感じ。以前、この鉄塔の下に鹿の骨がそのままの形で白骨化していて、遠目に人間のように見えたので、かなりびっくりしたのを覚えている。 登りはしんどい芦見峠までの林道も、降りはのんびりと歩く。空が晴れてきて、標高400mの越畑といえど暑くなってきた。宕陰小中学校まで戻ってくると、行きでは気づかなかった黄色い花畑が目に入り行ってみる。市民農園のところにオミナエシの花畑があり、減反政策の一端だろうか?花盛りだけど、これはどうするんだろう?切り花にして売り物にするには盛り過ぎているし・・。
結局デポ池に1時前に到着。5時間ほどの歩きでしたが、取り付きの標高が高いのと、流れの脇を歩いたので、それほど暑さは感じませんでした。やはり盛夏は沢歩きですね。 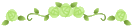
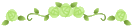
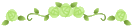
|
|||||||||||||||||||||||||||||

|

|
||||||||||||||||||||||||||||