
| 新春恒例 愛宕三山めぐり(小てつ NO.47) |

|
| 第2ベンチより市内 |

|

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平成26年1月3日(金) 晴れ 小てつ単独
コース: ◆愛宕寺横デポ地 7:15 〜 大杉谷 7:50 〜 月輪寺道出会い 9:05 〜 愛宕山三角点 9:28 〜 地蔵山ピーク 10:15 〜 10:45 〜 滝谷 〜 竜ヶ岳 11:30 〜 首なし地蔵 12:20 〜 八丁尾根 〜 八丁山ピーク 13:10 〜 デポ地 14:20 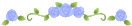
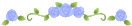
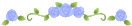
暮れに降雪があり、つい先日に訪れたばかりの愛宕山ですが、正月三日の恒例となっていますので、今年も調子見がてらに行ってきました。 朝はいつものように、7時に家を出てコンビニに寄り、7時15分にデポ地である愛宕寺横の空き地に到着する。登山靴に履き替えて、試峠に向かう。清滝の駐車場は、まだ数台の駐車しかなく、自転車バイク置き場にもまだ駐輪は無い。何か今年は閑散とした感じがする。
誰もいない堂承寺川林道をもくもくと歩き、大杉谷の取り付きに到着。ここでザックを下ろして衣服調節をする。今日は暖かくて、ここで2℃、ミドルのウエアを全部脱いで、ビーニーも暑いだろうと、吸汗のバンダナに変える。ストックを伸ばして登りにかかる。
大杉谷道は去年の台風の後、いくらか手が入ったようで、林道がきれいになっているような気がする。第1ベンチ、第2ベンチと雪は無く、しだの上にも霜は降りていない。結局つづら折れの途中まできて、やっと雪を見るような感じで、霜柱も見ることなく月輪寺道と合流する。月輪寺道に入っても、アイゼン、スベランゾーは必要なく、登山靴のままでジープ道まで登る。 ジープ道をいつものようにすぐ右に曲がり、三角点に向かう。流石にジープ道では雪が凍てつきガシガシ言うが、滑る感じではないのでそのまま歩く。三角点への急坂も、登りではアイゼンもいらないくらい。でも下雪が凍っていて、降りは着けた方が良い感じ。
三角点の急坂には、前日までの多くの踏み跡が残っている。でも今朝のはないみたいだった。三角点から写真を撮るが、今年の正月の写真も正面の木に雪の乗っていない写真となる。 ベンチまで降りて、アイゼンを着け、地蔵の方なら木の枝に雪も残っているだろうと、ザックカバーも着ける。 三角点の急坂を、久しぶりに着けたアイゼンを効かせてラフに踏んで降りていく。おっかなビックリになるのなら、アイゼンを着けた方が、断然早く歩ける。(当然か!)
竜への分岐にも多くの踏み跡が残るが、今朝のは無さそうだ。ところがジープ道から地蔵への分岐から旧スキー場跡の道に入ると、明らかに今朝のであろう長靴と思える踏み跡が、行ったのと帰ってきたのがあって、多分暮れに地蔵山に行った時のと同じパターンの靴跡に見え、この常連さんはいったい何時から登ってるんだと思う。 亀岡が見える鞍部から見ると、亀岡には低い川霧がかかり市内全体を覆っている。少しだけ見える周山方面も川霧が出ているようだ。(後で知らせていただいたJOEさん情報では、堂満からは琵琶湖にかかる雲海が、素晴らしかったそうだ。)
地蔵の反射板まで来ると、木々の小枝に小エビのしっぽがついていて、今朝早くは冷え込んだのだと思えた。でも陽のあたる場所のは、既に溶けかかっていて、気温が急激に上がっていることがわかる。手持ちの温度計では、ここで5℃を示していて、壊れているんじゃないかと思うくらい。滝谷への踏み跡がいくつかあり、変態が増殖しているのか?と思ってしまう。 地蔵山への登りの日当たりの良いところでは、地面が見えているところもあり、アイゼンをつけている小てつは、雪のあるところを選んで踏んで行く。途中のタイムは多少変わっていたが、地蔵ピークには去年と全く同じ時刻に到着し、驚いてしまう。時間は早いが、今年もここでラーメンタイムとする。
ラーメンを食べ終わるまで誰も到着無しだったが、出立の準備をしていると、親子と思われる二人の登山者が到着。二人連れは、地蔵ピークに展望が無いことを驚かれるが、「もう少し行った西向き地蔵あたりなら、ここよりは開けていますよ。」と言うと、「じゃあそこで食事を。」と向かわれた。小てつも出立し、滝谷に向かって、反射板ピークまで折り返す。 滝谷へのルートには、3、4人と思われる足跡が残っていたが、竜への登り返しには一人分の足跡しか無かったので、地蔵側から二人が降りて、一人は地蔵側に登り返したのだと思った。 滝谷の雪は少なかったが、登り返した竜ヶ岳手前のP900から竜の広場あたりの雪が一番多く残っていて、くるぶしが埋まるくらいの雪踏みを楽しむ。ただ、登山道と合流し、竜ヶ岳の登りにかかると、登山道に全く雪のないところが有り、一旦アイゼンを外す。
竜ヶ岳のピークにも誰もおられず。流石に降りでは必要だろうと、再度アイゼンをつけて、ピークから北向きに降っていく。やはり北側には雪が残るものの、シャクナゲのある岩場のあたり、標高880m付近までくると雪はなくなり、今度はアイゼンを外してザックに収納する。 去年、Fさん親子三人連れと遭遇したヒノキの植林地の急坂で、今年は二人連れが登ってくる。今年もやはりFさんで、何でも去年出会った男の子二人には振られてしまい、真ん中のお嬢ちゃんを連れてきたのだと言われる。中学生だと言われるかわいいお嬢ちゃんは、山で食べる美味しいラーメンに釣られて来たと言うことで、先々山ガールの素質十分アリな楽しみな人材です。 Fさんに滝谷など雪の情報を話し別れる。遅ればせながら、愛宕中毒患者のFさんの情報によれば、越畑から芦見峠間の林道が、去年の台風のため2ヵ所崩れていて、その場所を迂回するのにも一苦労いると言うことで、雪の季節ならなおさらだろうと思いますから、地蔵山に越畑から取り付くことを予定される方は承知してください。 竜の小屋には誰もおられず、火もおこっていなかった。首なし地蔵にたどり着き、今年はグチャグチャになっている梨ノ木谷に降りる気にならず、しばらく歩いていない「八丁尾根」で降りようと考え、谷山林道を降っていく。
首なし地蔵から谷山林道を10分ほど降ると、右手に地道の林道分岐がある。これが大伐採時の迂回路となっていて、本谷のグチャグチャが嫌な小てつはよくここを利用して梨ノ木谷の林道に降りていたのだが、おととしの豪雨のため林道への最終下降点がえぐれてガケになっているので、最後気をつけないといけなくなっている。また、その先も林道自体がグシャグシャになっているので、あまり気持ちの良い道とは言い難くなっている。従って、今年はその数十メートル先の、谷山林道が左にカーブするところの尾根から降る八丁尾根に入る。 八丁尾根の取り付きは、太い尾根の中央にくぼんだところがあって、どちら側を歩いても良さそうな雰囲気だが、左側の尾根は先の方で東に向きを変え、「恐怖の西の谷」に迷いこんでしまう可能性があるので、右側の尾根に入ることが重要である。
八丁尾根は、ヒノキと松の葉っぱが混在して落ちている京都北山らしい道で、台風や豪雨で荒れた様子もなく、昔と変わらぬ雰囲気を保っていた。途中溝状に掘れたところもあるが、ほぼ迷いようのない一本尾根なので、右手に愛宕の雄大な山容を眺めつつ、ほとんど水尾別れくらいまで南下するころに、八丁山のプレートを見ることになる。
プレートからすぐに、木にヤカンが引っ掛けられているところが分岐となっていて、梨ノ木林道に降り立つには、右手のうすい踏み跡の方に折れる。左手の太い踏み跡の方は、数年前に歩いた時には倒木がかなりあって、歩きにくい道だったと記憶している。また最後に川を渡渉しなければならなくなったと思う。
踏み跡がうすいのは最初だけで、斜面をつづら折れに降るようになると、道ははっきりとしてきて、標高450m付近から林道の215mまで一気の降りとなる。最後は去年の台風で吹っ飛んだ林道ゲートのすぐ下手に降りてくる。ここで、ザックカバーを外し、スパッツも外してストックを仕舞い、アスファルトの道を愛宕寺横のデポ地までひたすら歩く。
試峠のサルトリイバラは、今年はちゃんと実をつけていた。デポ地には14時20分に到着。結局去年とほとんど同じようなタイムで歩けました。八丁尾根を利用すると、アップダウンがあるせいで、少しばかり(20分ほど)梨ノ木林道を利用するよりかかるようですが、グチャグチャを見たくない人には、お薦めです。 帰宅して銭湯に行き、落ち着いてからFさんにメール連絡をすると、5時をまわっていたのに「今だ山中。」との事。例の月輪寺の時間通行止めのせいか、モミの木尾根で降りていますとの事だった。もうすぐ林道に降り立つとのことと、愛宕通のFさんのことなので、心配は無いと思ったが、何でも滝谷の降り登り返しでズルズル滑り、苦労して時間がかかったとの事だった。小てつが歩いた時刻から、1時間以上は遅く踏み込んだと思われることから、融雪が急激に進み、足元が悪くなってしまったのだと思った。Fさん、今度はお嬢ちゃんにも、山行同行振られることのないようにお祈りするばかりである。
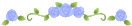
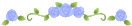
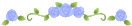
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||