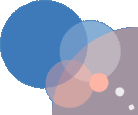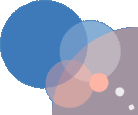雑誌・新聞レポ
『朝日新聞』 出典:01年1月28日付け 作成:サイトー 更新日:07年1月21日
『朝日新聞』 出典:01年1月28日付け 更新日:07年1月21日
21世紀メッセージ
朝日新聞: 企画・制作/朝日新聞社広告局
15歳で芸能界に足を踏み入れ、20世紀最後の10年間をスターとして突っ走ってきた稲垣吾郎に 新しい世紀に向けて心の中には何かが芽生えているのだろうか?というインタビュー。稲垣吾郎については「スタイリッシュな印象、ワインなど趣味の分野でみせるこだわり、エッセーなどでのぞく知性、若い女性ファンだけでなく大人たちをもひきつける骨太の個性が感じられる」と書いてあります。
【規則正しいものへのあこがれ】
自分のいる芸能界というのは、世の中と時間の流れが違う、というか時間の使い方に歯止めが無い。OKが出るまで納得がいくまでやる、または準備が遅れたりアクシデントがおきたり、さまざまな理由で時間が過ぎ、何でも有りの世界。
だからというわけでもないけれど、きちんと規律正しいことに魅力を感じる。朝起きると新聞が間違いなく配達されていて、銀行は決まった時間にシャッターが上がる。そういう基本の部分を毎日だれかが支えてくれているという安心感は大きい。
若い人たちが、何でも有りの時間の中で過ごしていられるのも、そういう規則正しい背景があるからで、そういう規則正しいものに頼っていられるから自由にやっていられる。
それで大人が今の若い人たちを見て、これから先は大丈夫かと不安に思っているかもしれないけど、自分も含めて、きちんと働いている大人、規則正しい社会をどこかで評価していると思う。
一人一人が働いている姿はあとに続く世代に伝わるはずだし、21世紀だからって基本は変わらないと思う。
【自分の絵の具】
はじめはSMAPというグループでの仕事が主体だったけれど、だんだん個人で仕事がくるようになった。グループのメンバーはみんな個性が強いし、その個性を生かした仕事で評価が集中すると、正直やられたと思って悔しかった。それは一箱の絵の具の色を取り合っているような気分。自分が狙っていた色を他のメンバーに持っていかれてしまったから、自分は残りの色で勝負するしかないと思ってしまって焦る。他の人との違いをどう表現するか、残ったどの色を使ったらいいのか不安になった。
でも今になってそれは表層的な部分のことであったということが分かった。あいつがグレーなら自分は茶しかないと思いつめてその色になりきろうとする自分が不自然だと気付いた。もしかしたら、絵の具箱はそれぞれ一人ひとりが持っているのではないか、自分は絵の具を混ぜ合わせて好きなグレーを作り、自分の絵を書いていけばいいのではないかと納得してから、とてもラクになった。
限られたパイを取り合うことじゃなく、それぞれで作ればいい。一瞬で勝負をつけるのではなく、きちんと色を重ねていけば稲垣吾郎になるんだ。だから自分に必要なのは、いい絵を描けるように絵の具を増やしたり、色の混ぜ方を工夫したりすることなんだ。
同じ時代を生きて、同じ場所にいても、入ってくる情報は違うし感じ方も違う。好きなものに個人差があるんだし、それを変える必要もない。「ぼくはぼくなり」って落ち着いていればいいと思えるようになった。焦って探し回っても自分用の個性なんてどこかに落ちているわけではないから。いろいろ選択を間違って失敗もするけれど、自分は螺旋階段を上るようにして今日まで来たと思う。一応は上ってきてると思うな(笑)。
【どこか図太さも大切】
仕事はきちんと精いっぱいにやるということは肝に銘じているけれど、自分のやった仕事がどこにどんな形で波及しているのかはつかみきれない。自分の見えないところで、どんな稲垣吾郎がいるのか分からないという恐怖に似た思いにとらわれることがある。たとえば、ドームのコンサートと小さな劇場での舞台とでは、多分観客が受け取る印象が随分違うと思う。それぞれで受け取った印象が一人一人の心の中で増殖して、自分とは違う稲垣吾郎が存在し始めるってコワイじゃないですか(笑)。
でも多かれ少なかれ、そういうことはあるし、話がうまく伝わらなくて誤解されたり、何かで噂になってしまうとか、それって自分の正しい姿じゃないと愕然とするけれど、いちいち訂正しに行くわけにもいかない。
だから誤解されたり、違う自分が増殖されるのは当たり前のことだと図太く考えることにした。幻影ではなく、ちゃんと自分がここに存在していることを自分で分かっていれば何の心配もない。だって仕方のないことだから。
舞台の緊張感とか臨場感がとても好き。ぎっしりと書かれたセリフを言いながら同時に動き回るなんて本当に大変なんだけど、生身の自分が目の前の観客と同じ空間にいるっていうのはからだがふるえるほど緊張する。セリフを忘れるんじゃないか、トチるんじゃないかという不安に取り付かれたら恐怖だけど、それを乗り越えて拍手をもらうとちょっと感じたことのない充実感が押し寄せてくる。「お前はいけるぜ、吾郎」って思える。
ノアの方舟みたいに、地球の未来に必要な職業だけを選ぶとなったら、自分たちのような歌い手や役者は真っ先においていかれるかもしれない。でも、いろいろな価値観が一緒に混じり合っていけるといい。
そして、一生懸命仕事している人がバカをみない、ちゃんと報われる時代であって欲しい。(談)
ANGEL'S COMMENT:
とても素敵なレポをサイトーさんから頂いたので、ぜひ皆さんに読んで頂きたくUPさせて頂きました。上手く編集されているので、そのまま全文を転載したかのように見えますが、1人称で書かれていたのを3人称で統一して、吾郎らしい丁寧語での受け答えを断定言葉に置き換え、文も編集頂いてます。
相変わらず、インタビューへの受け答えが完璧な吾郎で、それだけでも読むのが嬉しくなりますが、絵の具のくだりは「そんなこと考えてる時期もあったんだなぁ」と思うと同時に、とても正直に答えているのが好感が持てます。彼らしいインタビューですよね。
このページのTOPへ
|